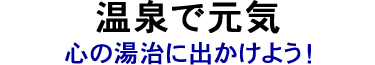|
第3回
湯守のいる宿
湯守(ゆもり)という言葉をご存じですか?
何軒も宿のある温泉地では、1つの源泉から
各宿へ分湯している場合が多いので、
必ずしも宿の主人が湯の管理をしているとは限りません。
でも、一軒宿と呼ばれる小さな温泉地のほとんどは、
自家源泉を保有しています。
温泉の湧出地から
宿の浴槽へ湯がたどり着くまでの一切の面倒をみる、
いわゆる「湯守」のいる宿です。
湯守とは、読んで字のごとく、湯を守る人のことを言います。
いい湯守は、湯に手を加えることを嫌います。
自然に湧いた湯を、動力を使わずに、
そのままの姿で浴槽まで流し入れたいからです。
しかし浴槽内の湯の温度は、季節や天候により微妙に変化します。
ですから湯守は、
窓の開閉や注ぎ入れる湯量を調節することにより、
一年を通じて適温を保っているのです。
群馬県の北西部、みなかみ町に
法師温泉「長寿館」という一軒宿の旅館があります。
その昔、旧国鉄のフルムーンキャンペーンポスターで、
俳優の上原謙と高峰三枝子が入浴した温泉と聞けば、
思い出される人も多いかと思います。
ここは全国でも1%未満という、
数少ない浴槽直下の足元から源泉が湧く温泉です。
この「足元湧出温泉」は、湧き出した湯が
直接すぐに人肌に触れるため、
熱過ぎても、ぬる過ぎても存在しません。
ちょうど41〜42度の適温の湯が湧出する温泉にのみ可能な、
まさに“奇跡の温泉”なのです。
宿の創業は明治8(1875)年。
6代目主人の岡村興太郎さんは、
湯守の仕事について、こう言いました。
「温泉とは、雨や雪が融けて地中にしみ込み、
何十年という月日をかけてマグマに温められて、
鉱物を溶かしながら、ふたたび地上へ湧き出したものです。
でも、地上へ出てきてからの命は、非常に短い。
空気に触れた途端に酸化し、老化が始まってしまう。
湯守の仕事は、時間との闘いです。
いかに鮮度の良い湯を提供するかなんです」
さらに岡村さんは
「湯守は、温泉の湧き出し口(泉源)だけを
守っていればいいのではない。
もっとも大切なのは、温泉の源となる雨や雪が降る場所。
つまり、宿のまわりの環境を守ることだ」とも言いました。
周辺の山にトンネル工事や土木工事をされれば、
湯脈を分断される恐れがあります。
またスキー場やゴルフ場ができれば、
森林が伐採されて山は保水力を失い、
温泉の湧出量が減少することもあるのです。
いい温泉は、いい湯守により、
守り継がれているということです。
|