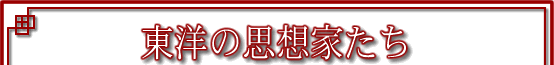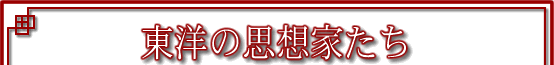|
サマセット・モームによると、読書にはおよそ三つのタイプがあるそうである。一つは娯しむために読書をするタイプ。もう一つは読書によってなんらかの知識を得ようとするタイプ。最後はそのどちらにも属さず、たんに惰性によって読書をするタイプ。そして、モーム自身は最後のタイプに属すると自分で告白している。
まだ学生であったじぶん、私は相当読書欲が旺盛で、それがたまたま知識欲と並行していたので、モームの分類に従えば、一応第二のタイプに属していたように思われる。当時、高校生のあいだでは西田幾多郎『善の研究』とか倉田百三『愛と認識との出発』など主として岩波書店をホクホクさせるような種類の書物が流行していた。他人に遅れをとるまいという競争意識から、私もそれらの書物を手にとってみたが、私の頭脳はよほど哲学的思考に耐えないようにできていたとみえて、たいていは途中で投げ出してしまった。
しかし、当時の私は自分の頭脳をいくらか過信していたので、それは自分が悪いのではなくて、相手が悪いのだろうと思っていた。私はべつの方向から書物という人類の知的遺産に近づこうと考えた。ちょうど、そのころ、『世界文学をどう読むべきか』と題するへルマン・ヘッセの本が出た。私はヘッセの小説をそれまでに数冊読んでいて、そのロマンチックな性格には大いに共鳴したが、その少女趣味には少しく辟易していた。けれどもこの本は、少なくとも少年期から青年期へかけての私にとっては、読書をしていくうえでのよい手引となった。
二十歳前の貧弱な頭脳で、数百ないし数千年の風雪に耐えてきた書物がどの程度に理解できたか、今日の私からすれば、著者たちにむしろ気の毒な気もするが、とにかく、私はヘッセの案内に従って、手当たりしだいに乱読をしていった。私は夜の図書館に通ったし、また学資の許す範囲内で、自分の本棚を埋めようとも努力した。その反動がきて、書物の虫になっている自分に急にいや気がさし、せっかく、昼食代を節約して買い込んだ書物を全部人にタダであげてしまったこともある。(手元不如意な貧乏書生だったころも私は本を売ったことがない。)
さて、知識欲の旺盛な時代にはおもしろくない書物でも、ある程度は我慢のできるものである。ところが、おもしろいおもしろくないは、相手にもよるが、実はこちらの精神年齢にもよるものであることを、ことに若いときは信じたがらない傾向が、少なくとも私の場合にはあった。たとえば、セルバンテスの『ドン・キホーテ』は不朽の傑作と聞かされていたけれども、学生時代の私ではどうしても歯が立たなかった。いつも水車小屋のところまでくると、ドン・キホーテよりもこちらのほうがヘトヘトになって、冒険心も根気も尽き果ててしまったものである。
ところが、書物のなかの人間よりも、実社会の人間に数多く接するようになると、ドン・キホーテ的な存在が無数にあるばかりでなく、自分も含めて人間はみなある意味でドン・キホーテであり、ことに年をとるにつれて、いっそうドン・キホーテ的傾向が強くなることに気づいてくると、退屈でならなかった『ドン・キホーテ』が読むに耐える書物となったばかりでなく、ばかげた長ゼリフのなかにかえって興味のわくのを感じて、文字どおり一読巻をおくあたわず、孔子の表現をかりるならば、読み終わるまで「肉の味を忘れ」るぐらいであった。残念ながら、年齢や体験は争えず、書物に対する評価のなかに逆に自分が量られていることに気づかざるをえない。
今日でも自分の知識欲が衰えたという自覚はないが、その代わり、自分なりに妙な偏見が固まりつつあるので、「ためになろう」と思って読書をしようとする気持はますます薄れ、また義理で人の本を読むのもご免で、おもしろくない書物はすぐ途中で巻を閉じてしまう。
職業上の必要から読書をする場合も、自分が興味を抱いていることにかぎられ、たまに強制されることもないではないが、それは長続きがしない。したがって、読書は私にとって依然人生の楽しみのひとつであって、それを一種の苦行に変えてしまう気持はさらにない。
|