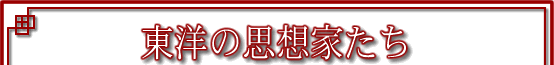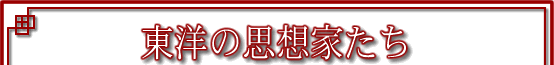|
韓非が温情主義、刑罰主義を否定し、厳罰主義、重刑主義を提唱したのは、もとより刑法を犯人に対する復讐手段と考えたわけではない。それどころか、彼は犯人の動機いかんにかかわらず、彼らを一律に犠牲に供することによって社会秩序を維持すべきであると考えた。彼の眼中には乱をなす者、盗みをなす者に対するいささかの憐憫の色もなかった。
憐憫の代わりに怒りがあった。彼の怒りを支えていたものは、そうした違法行為がやがて国家を弱体化し、外国の侮りを買うという事実にほかならなかった。
国の富強ないし独立なくして国民の幸福はありえないという立場に立たされた彼は、この至上目的のために少数者を犠牲にするのはやむをえないと思ったのである。
「古い諺にもあるように、政治とは洗髪のごときものである。そのために脱毛があっても、髪毛を洗わない者はいない。脱毛を惜しんで洗髪の利を忘れるのは権を知らない者である」(六反)
はれものができたら、うみを出さなければならない。病気になれば苦い薬を飲まなければならない。うみを出したり、苦い薬を飲むのが苦痛だからといって、それをやめれば、健康を恢複することはできないであろう。
こうした考え方は、一匹の迷える小羊のためには、九十九匹をおっぽり出しても、と考えるキリスト精神とまったく対蹠的である。なるほど一匹の小羊のために受難をも辞さない崇高な精神は、九十九匹の涙をさそうにじゅうぶんであろう。しかし、迷っても救いの道があることがわかれば、九十九匹がみなそれぞれに迷いはじめ、九十九匹の羊を飼うことはもはやできなくなる。つまりキリストを崇めるのも羊なら、キリストを苦しめるのも羊であり、韓非をして憎むべき意見を吐かせるのも、羊の卑しむべき性格にあるといわざるをえない。
「重刑だからやめたほうがいいぞと思う者でも、軽刑ならやってみようかと思うことがある。(たとえば国民の血税を一億円つまみ食いしても、数年の服罪と仮出獄の見込みがあれば、双方を秤にかけてみる者があらわれる。)しかし軽刑でもやらない者は、重刑ならもちろんやらないにきまっている。だから重刑をもって臨めば法律を犯す者はなくなる。
法律を犯す者がなくなれば、重刑主義でも人民を傷つけることはないであろう」(六反)
だいたい、人民は重刑をきらうものである。そして軽刑は悪党に有利なものである。軽刑ならば罪をあなどり、悪に誘われる可能性が強い。かくて悪事はあとを断たなくなる。
ちょうど、人間は高い山につまずくことはないが、蟻塚のような小さなものにつまずくようなものである。たいしたことがないように見せかけて、つまずけばこれを罰するのは、落とし穴を設けて人民をおとしいれるようなものであろう。
「ところが、今日の学者先生はみな"愛の書"をお手本とし、現実を見つめようとしない。為政者が民を愛しないで、苛斂誅求、税金をしぼりあげるがために不平不満が起こり、内乱が起こるのだと説く。あたかも衣食をたらし、愛を加えれば、刑罰を軽くしても世の中が治まるかのように思っている。この考え方はまちがっている。だいたい、私が重刑主義を唱えるのは、もちろん衣食をたらしてのちの話である。衣食をたらし、愛を加えても、刑罰を軽くすれば乱れるものである。金持の子弟を見てみるがいい。彼らは金に不自由しないが、不自由しないがゆえにかえって金を軽々しく扱っている。金を軽々しく扱えば、ぜいたくになるし、これを大事にすると、かえって言うことをきかなくなり、生意気になる。ぜいたくをやれば貧乏になるし、生意気になれば、素行がおさまらなくなる。これ衣食たりてかえって利を軽んずる典型というべきであろう。だいたい、人間は食うに不自由しなくなれば怠け者になる傾向があり、政治が寛大であれば、かってなことをやる傾向がある。衣食がたりて、しかも勤勉なのは神農のごとき人物であり、政治が寛大でしかも法を犯さないのは曾参史魚のごとき人物である。一般人民に神農曾史ほどの人格を期待しえないことは明らかであろう」(六反)
「むかし、鄭の宰相子産は臨終の床で、游吉に向かって言った。私の死んだのち、あなたは必ず私の跡を継ぐことになろう。そのときは必ず重刑主義でおやりなさい。火というものは形は厳しいから、かえって火傷をする人が少ない。水は柔らかで、たいしたことがないように見えるから、おぼれ死ぬ者が多い。どうかあなたは温情主義で国民をおぼれ死にさせないよう刑罰を厳にしてください、と。ところが子産の死後、游吉は厳刑を行なうに忍びなかった。そのため鄭の少年たちは徒党を組んで盗みを働き、灌沢を根拠地として国じゅうの禍となった。游吉は軍隊を率いてこれと戦い、一昼夜かかってやっとこれにうちかつことができた。そのとき、彼はもし子産の言うとおりにしていたらこんなことにならないですんだだろう、と慨嘆したのである」(内儲説上)
こうした実例が韓非の思想を裏付けていること、そして、それじたい、人間性の一面を鋭く突いていることは、遺憾ながら否定することができない。けれども、それが人間性のすべてでないこともまた事実であり、現実政治が韓非的思想のみによって動かされてこなかったことにも、留意する必要がある。むしろ韓非の思想は、その真実性のゆえに、つねにつねに敬遠されてきたとみるべきであろう。
|