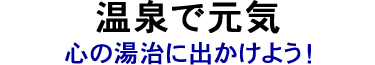|
第17回
内湯と内風呂
とかく「内湯」と「内風呂」を
混同している人が、多いようです。
昔々、先人たちは、
温泉が湧き出る場所に、湯小屋を建てました。
これを、大湯(共同湯)といいます。
旅館は、あくまでも宿泊をし、食事をするところ。
湯治客らは、手ぬぐいをもって、
大湯へ湯をもらいに出かけて行ったのです。
やがて、財力のある旅館は、
温泉を引いて館内に浴室を設けました。
これが「内湯」です。
<大湯(外湯)>に対して、そう呼ばれました。
今では旅館の中に温泉を引いた風呂があるのは
当たり前になりましたが、それでも時々、
湯治場として栄えた温泉地へ行くと、旅館の玄関前に
「内湯あります」と書かれた古い看板を見かけることがあります。
これなど、湯治場風情の名残だと言えるでしょう。
これに対して「内風呂」は、新しい言葉です。
高度成長期以降、温泉地はどこも、こぞって大浴場を造りました。
旅行会社とタイアップして、団体客を収容するためです。
これにより温泉の湯量が足りなくなってしまった温泉地もあり、
新たな源泉を求めてボーリング(掘削)をするという
本末転倒な現象が、全国各地でくり広げられました。
やがて時代は、平成へ。
バブル期を迎え、ますます温泉施設はエスカレートしていきます。
露天風呂の出現です。
「露天風呂がなければ、客が来ない」とまで言われ、
小さな旅館までもが屋外に風呂を造りだしたのです。
「内風呂」とは、この<屋外にある露天風呂>に対して、
屋内にある風呂のことを言います。
みなさんも、旅館のパンフレットに
「内風呂:男1・女1、露天風呂:男1・女1」などと
施設案内が書かれているのを見たことがあるはずです。
稀にですが、「共同浴場:1(宿泊者無料)」と書かれている
パンフレットを見つけるときがあります。
宿の近くに、昔ながらの大湯があるのですね。
外湯がある温泉地は、古くから湯治場で栄えた証拠です。
ですから外湯に出合うと、ちょっぴり得した気分になります。
|