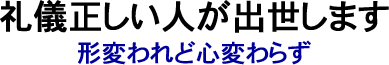|
第174回
正しい参拝と神道への知識
新年、皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますか?
私は、今年発売となる4冊の本の執筆やら確認やら、
撮影やらに追われる毎日です。
そんな中、お正月といえば『雑煮』。
お正月にいただくご馳走のひとつです。
そのいわれは様々ですが、
おおみそかに年神様にお供えした野菜や餅を元旦におろして、
若水を使って
ひとつの鍋で煮て食べたのが始まりとされています。
若水とは元旦の早朝に初めて汲む水のこと。
何事も『初』という響きはいいですね。
そして、お正月といえば『祝い箸』。
お正月やお祝いの席で使われる、
両方の端が細くなっている箸を祝い箸と言います。
お正月は年神様(としがみさま)をそれぞれの家に迎え、
おせち料理を年神様と人間で一緒に食べると考えられており、
一方の端を年神様が、
もう一方の端を人間が使う
「神人共食(しんじんきょうしょく)」という意味をもちます。
この祝い箸が折れるのは縁起が悪いとされ、
丈夫な柳が材料として多用されます。
そのため「柳箸(やなぎばし)」ともよばれます。
さて、皆さんは初詣には行かれましたか?
ところで神社とお寺の違いをご存知ですか?
寺は仏になるための修行をしたり、
仏教を布教する建築物です。
寺という言葉は中国生まれで、
そもそもは役所のことでしたが、
仏典の漢訳をする際に役所をその作業場所としたため、
僧がいつもいる場所を、一般に寺と呼ぶようになりました。
神社は神を祀る場所で、
神体となる自然物や歴史に名を残した偉人が祭られています。
古来、日本では神様を祭るのに建物などを建てず、
御神体となる山などを直接拝んでいました。
現在でも拝殿だけで本殿を持たず、
御神体を直接遙拝(ようはい)する神社は数多くあります。
昨年、藏原これむつ氏の『神道的生活が日本を救う』の
特典映像をご覧になった方は正式な参拝ができたと思います。
参拝とは、お正月や春秋の祭礼をはじめ、
初宮参りや厄祓いなど人生の節目に神社へと赴き、
様々な願いを神にお祈りする行事です。
参拝時に、
もっとも大切なのは真心をこめてお参りすることです。
心身ともに清浄にし、身なりを整えて参拝をする。
これは、参拝のときのみならず、
日々の生活も同様のことですね。 |