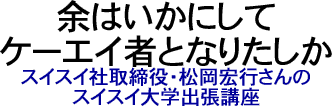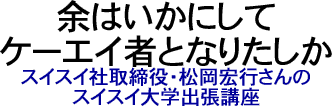|
第83回
ブランドケーエイ学33:なにをといかに。
 さて、おなじく共感をベースにしても、面白い方向ではなく、美しいもの、きれいなもの、すっきりさわやかなものというトーンで一貫させて、企業イメージやブランド化につなげようとする方向がある。 さて、おなじく共感をベースにしても、面白い方向ではなく、美しいもの、きれいなもの、すっきりさわやかなものというトーンで一貫させて、企業イメージやブランド化につなげようとする方向がある。
中国モデルのサントリー・ウーロン茶が、最も成功している事例で、一連のソニーの広告もこれ。ビン探しの「いいちこ」ポスターもこの仲間だね。
この方法では、タレントは必要ない。長期的に継続することが効果的で、クライアントには信念と辛抱がもとめられる。同時に、じゃっかん印象が弱くなり、うもれがちになる傾向は避けがたい。
おもしろ型と企業イメージ型、これらの共感広告にたいして、明快な特徴のある商品について、訴求点を絞りこんで勝負をかけるタイプを直球広告とよぼう。
この点、フォルクスワーゲンのCMは上出来だ。ある車種では、冬山のそり競技のコースを下から上に逆走させて、商品の頑丈さ・タフさを単純に訴えている。絞りこまれた事実ベースの訴求点とレトリックががっちりと結びついて、とても印象が強い。
黒ラベルの「温泉卓球」は、共感広告の歴史的名作だった。しかし、どんなに好感度が高くても、売上げに結びついたのかどうかというと、やっぱりスーパードライが盤石だったわけだ。温泉卓球が黒ラベルの「何を」訴えたのか? そこが弱かったので
はないだろうか?
かたやスーパードライの広告は、表現こそたいした工夫はないけれども「鮮度、鮮度、鮮度」の一点ばり。連呼に近い直球だ。しかし事実をベースに、在庫管理から物流の方法、荷物にかけるホロにまでこだわったと主張されると、消費者としては、その意気込みに気押される。いやサッポロだってそれくらいやってたかもしれないが、先に言った者が勝ちだ。
趣味の表現ではなく、成果を求められるのが広告である以上、ほんとうは「いかに」よりも、「何を」が重要なのではないだろうか。
レトリックだけで、一流の広告効果を達成することは難しい。これを決めるのは、広告制作者ではなく、クライアント自身になる。
ブランド広告には、まず、商品に事実がなければならない。商品開発が、企業姿勢や経営と一緒にあってはじめて、立派な広告ができる。
いま日本で最高のブランドはソニーだろう。大賀典雄さんの「私の履歴書」を読むと、こういうことをしっかりやったんだなあと、よくわかる。
|