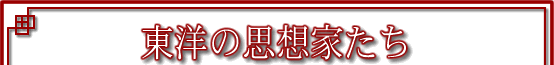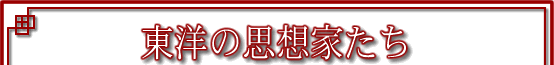|
| 聖 人 の 座 |
私は聖人というものを信用しない。今日、われわれの概念となっている聖人はいっさいの悪を超越した、極端に理想化された存在で、人という字が付いていることによって、わずかにわれわれと結びついているにすぎない。
どうしてそんなものがわれわれのあいだに存在してきたかということは、どうして西洋人のあいだで神の座が設けられてきたかということと同じ性質の問題である。たぶん、それは人間自身の力ではどうにもならない人問の弱さや儚さがいちばん重大な原因であろう。
ただ、われわれの場合には、心的であるよりは知的な形をとって現われた。これはわれわれの文明を西洋のそれから区別する最も大きな特徴であるが、長い歴史のあいだに、キリストによって占められた神の座が何度となく揺らぎ、今日に至ってかつてないほど激しい揺らぎ方をしているように、聖人の座もしだいに無力化してきている。
今日では儒教の文明史上で果たしてきた功績よりも罪悪のほうが問題にされ、二千五百年のあいだ、この聖人の座にすわらされてきた孔子を引きずりおろそうとする考え方がなかなか盛んである。
私の考えによれば、聖人の座というものはけっしてすわり心地のよいものではない。試みに日本の国会で、天皇のために用意されているイスを見てごらんなさい。あのイスがふつうの家の応接間に並んでいるソファーよりもすわりよいと思う人は誰もいないであろう。
それは、あのイスがわれわれが生理的に楽にすわれる高さよりも、よほど、高く作られているからであるが、人間が最も威厳のあるように見えるのは、この姿勢以外にないのである。二千五百年もこのイスにすわらされて動脈硬化をきたさないほうがむしろどうかしているし、ましてや自分の意志によってこの座に就いたわけではないのだから、孔子のほうで聖人の座は願い下げにしたいと思っているにちがいないのである。
なぜ、私がそんな考え方をするかというと、現代人にとって最も魅力のないのが聖人の座であり、そこにすわらされることによって孔子は得をするよりも損をしていると、私が思っているからである。私でさえそう思う世の中だから、私よりはるかに神経質で、リアリストで、しかも外交家であるところの孔子がそれに気づかないはずがないであろう。
ところで諸君は、私が孔子を――あの老いぼれの、時代遅れの爺さんを――背広を着け、頭髪を七三に分けた現代の紳士に仕立てあげる魂胆だとにらんでいるかもしれない。ところが、私の知っている孔子は、仁徳のある男でもなければ、清廉潔白な男でもなく、卓見はあったが、相当のやかまし屋で、そのために、あまり恵まれなかった一人のインテリなのである。少なくとも『論語』を読んで私が受ける印象はそうであり、そうであればこそ、孔子のためにひと肌脱ぐ気になった。
われわれの文明上の遺産がどんなものであったかを、主としてわれわれの文明に魅力を失った人々に、できるだけ印象的な手段で知ってもらうのか私の目的であるが、この目的のために私は『論語』の考証学者たちから見れば相当向う見ずの冒険をすることになる。
なぜならば『論語』の注釈書は、中国、日本および西洋のものを合わせておよそ七、八百種もあるが、学者たちの意見によれば、『論語』二十篇は寄せ集めであり、その中には後世になって付加された部分も相当あるはずで、ことに聖人としての孔子に都合の悪い季氏(きし)、陽貨(ようき)、徴子(びし)などの諸篇は最も怪しいものとされているのに、私にとって最も興味のあるのは、これらの怪しげな部分だからである。
これに対する私の回答は、第一に孔子の言行を知るうえにおいて『論語』以上に信憑すべき資料が現存していないことである。『論語』二十篇はきわめて暖昧な断片の寄せ集めであり、字義の解釈いかんによっては意味深長な内容を持っているが、これは孔子が体系的な理論の持主であるよりは、その場その場で自已の判断に頼った直感力の鋭い男であった証拠であり、仔細に読んでみると、孔子の自信にあふれたことばもあれば、詠嘆のことばもあり、ユーモアもあれば、怒りもある。そして、聖人どころか、ふつうの常識ある紳士なら首をかしげるような行動をとるところが再三ならず見いだされるのである。『論語』を金科玉条とする立場からすれば、これは、後世の人が蛇足を付けたことになるかもしれないが、孔子の言行をその時代的背景と切り離して考えることは不可能である。そのために、私はできるだけ孔子の時代の政治的社会的背景を知ろうと努めた。『左氏伝』に記述されている春秋の時代は多分に小説的であるが、しかし、両者を比較対照すると、孔子という人間がかなり明確な形で浮かび上がってくる。
第二に、かりに孔子に不利な部分が後人の付加したものであるとしても、それによってわれわれは孔子が彼の門弟の一派や同時代の彼の敵役の目にどう映っていたか、知ることができる。孔子自身の言行よりも、敵や門弟という鏡に映された映像のほうがより真相に近い場合があるはずである。
およそ以上のような態度で、私は論語に臨んだ。私の目に映った事象をつなぎ合わせて一篇のいわゆる小説に仕上げることはさほど困難ではないが、私の意図は『論語』の現代的な読み方である。相撲の世界では稽古場で胸を貸してくれた相手を、本場所で負かすことを「恩を返す」というそうだが、幼いころ、私に退屈な『論語』の手ほどきをしてくれた漢学者先生に「恩を返し」たい気持も多分にある。もっとも、時代というものは川の流れのようにとどまることを知らないから、いくら巧みな読み方をしたところで、「論語読みの論語知らず」のそしりはしょせん免れえないであろう。 |
|