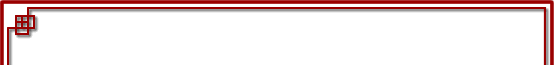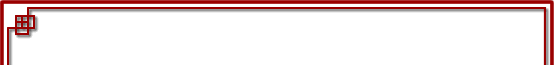|
その点、はなはだ皮肉な現象であるが、孔子は実際家たることをモットーとし、実際政治に恋々としたが、必ずしも実際的な手腕が伴わず、結果としてむしろ万年野党の立場に立たされた政治の落第坊主であった。ところが、彼が実際家たちから迂遠だといってバカにされる原因となった数々のお題目は、彼の死後、彼の弟子たちによって金科玉条とされるようになった。そして、それに付和雷同したのは、荘子が看破しているように、ほかならぬ悪党どもである。
荘子のほんとうの敵は、おそらくこれらの悪党どもであったにちがいない。悪党どもを敵にまわせば、彼らが偶像視するものを破壊する必要が当然生じてくる。作戦として、荘子は孔子をあるいは敵とし、あるいは味方とし、孔子の偶像を分裂させることに努めたのであろう。
この意味で、荘子は孔子の「反」であり、孔子の存在なくして、荘子を理解することはできない。ちょうど、共産主義が資本主義の「反」であり、資本主義が民主主義を看板にすると、共産主義は資本主義的民主主義を否定して、自分のほうこそ真の民主主義であると主張しているようなものである。たとえば、孔子は人倫道徳を提唱した。すると、老子は道徳無用を唱え、「大道廃れて仁義あり、知恵出でて大偽あり、六親和せずして孝慈あり、国家昏乱して忠臣あり」と言った。しかも、道徳無用を主張する『老子』に「道徳経」という名前がついているのである。道徳無用論が道徳論に先行するわけがないし、また一元論が多元的意識に先行するわけがない。こうして論理的な類推からしても、『老子』は孔子よりも年代的に遅れた存在であり、『論語』を意識においてそれより古い著述であることを示すために、ことさら簡潔難解な文章をもって書かれたとしか思えないのである。それが荘子自身によって書かれたものであるか、あるいは「荘子的」人物によって書かれたものであるか、今日これを知るてだてはないが、にもかかわらずその反語的性格は否定しえないであろう。すなわち反社会性、反政治性、反文化性は老荘哲学のそもそもの出発点だったのである。
孔子は社会秩序を形作ることを主張した。すると、荘子は社会秩序から人間を解放することを主張した。孔子は善政を政治のモットーであると主張した。すると荘子は、政治は本来愚劣で陰険なものにすぎないと反証した。また孔子は礼――今日でいえば、文化を重んじた。すると、荘子は、文化が退化にすぎないことを証明して、人間性の自由を主張したのである。
孔子の哲学は、たとえば、山登りのようなものである。一歩一歩と高きへ登れば、それだけ広い世界を見渡すことができる。しかし、荘子は山を登れば登るほど空気が希薄になって人間が住めなくなることを指摘して、人生は河を下るにしかず、と主張した。
山へ薪を取りに行くのが男性的で、河へ洗濯に行くのが女性的であるかどうかは、大いに議論の余地があろうが、老荘は柔らかい水のほうが堅い金石よりもむしろ強いと考えたのである。
「上善は水のようなものである。水は万物を潤して、しかも争わず、低いところへ流れて行く。それゆえ、道に近い」(老子上篇第八)
「大河や海が百谷の王であるのは、もろもろの谷よりも低いところにあるからである。それゆえ、聖人が人民よりも上になろうと思うならば、言うことは人民よりも低く、また人民よりさきになろうと思えば、その後ろから進まねばならない。こうすれば、上にいても人民は負担を感じないし、前にいてもじゃまにならないから、人民は喜んで彼を推薦するであろう。かかる社会には闘争はないのである」(同下篇第二十九)
「雄は強いものであることを知って、雌の弱きを守れば、天下の谷になることができる。天下の谷になれば、徳の至れるものであるから、赤児の魂に帰ることができる」(同上篇第二十八)
こうした闘争への嫌悪、平和主義、ことなかれ主義は、実は中国の社会がむかしから峻烈な闘争の場であったことを示すものにほかならないが、しかし、人間と生まれて、人間世界から隔絶することは実際問題としてなかなかできない。なぜならば、
「越に流されて国を離れた者は、国を出て数日のあいだは知人故旧に会って喜び、国を去って旬日たつと、かつて国で見たことのあるものを見て喜ぶが、それが一年に及ぶと、かつて国で見た人たちに似たものを見ても喜ぶようになる。人を離れることが長くなればなるほど、人を恋うる気持はいよいよ深くなる」からである。(徐無鬼第二十四)
そこで低きにとどまるということは、人間に愛想をつかして、人里離れた寒村に住むことではなくて、言ってみれば、人のたくさん住む町中の人群れのなかにまぎれ込んでしまうことなのである。そして、与えられた環境に適応して、それなりに満足することを知れば、この世もまた楽しいではないかという一種の精神的享楽主義の心境に到達する。
人知の進歩はかぎりないといったところで知れたものだし、人生の幸福は、まあ、今夜の飯のおかずでも考えているような平凡な生活のなかにあるのだろう――というのが、東洋的なロマンチシズムの帰結なのである。
|