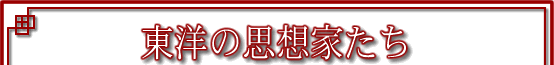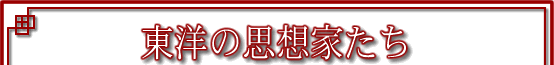|
醜悪な現実を前にして、怒り心頭に発することこそあれ、そこから一歩も退こうとしなかったのが韓非の態度であった。そして、その点が荘子ときわめて接近した社会観をもちながら、しかも袂を相分かつ理由となっている。この意味で韓非は徹底的な現世主義者であり、その理論が始皇帝のような覇王に愛された事実から見ても、孔子などよりもはるかに実用的であったことがわかるであろう。
しかし、いかに良薬であろうとも、それを用いる者がなげれば、しょせん効果がない。
マスターべーション哲学の域を脱するためには、当時の杜会情勢のもとでは、とにかく、君主に採用されることが先決条件であった。そして君主に採用されるためには、相手を説得しなければならないのである。
韓非のもう一つの有名な文章「説難(ぜいなん)」は、説得術のむずかしさについて述べたものである。
「むかし、鄭の武公は胡を征伐しようと思った。そこでまず自分の娘を胡の王様に嫁がせて、その歓心を買った。ついで群臣を集めて、兵を起こそうと思うが、誰を伐つべきであるかと聞いた。大夫の関其思(かんきし)はその意向を知っていたので、胡を伐つべきです、と提案した。すると武公は、胡は兄弟国であるのに、胡を伐てとはなにごとだと怒って大夫を殺した。胡の王様はそれを聞いて、鄭を味方と信じ込み、これに備えなかったので、ついに鄭に滅ぼされた」(説難)
およそ説くことのむずかしさは、自分の知識や思想を明確かつ存分に述べて相手を納得させうるか否かにあるのではない。相手が何を考え、なにを欲しているかを察して、自分の説をいかにこれと合致せしめるかにあるのである。もし相手が名誉を欲しがっているのに、これに対して実利を説けば、下賎なやつとさげすまれて遠ざけられるし、反対に相手が実利を欲しがっているのに、名誉をもってこれに説けば迂遠なやつだと敬遠される。また陰では実利を欲しがっているのに、表面では名誉を望んでいるようなふりをする君主がある。こういう者に対して名誉を説けば、口では先生、先生とたてまつるが、裏では役立たずだと思われ、利益を説けば、陰でこっそりその献言を採用するくせに、面と向かっては相手にもしない。
また君主の密議に参画するようになると、秘密がもれた場合、たとえそれが自分の口から出たのでなくとも生命は危ない。君主が他人事に託して述べたことでも、こちらが了解すると、相手の弱点を知ったことになるからこれも危ない。また他人の想像したことが偶然事実と一致した場合も、自分がもらしたものと邪推される。
「宋の国のある金持の家で大雨のために垣根が崩れた。息子が垣根をなおさないと泥棒が入りますね、と言ったが、隣家のおやじも同じことを言った。はたしてその晩、泥棒がはいってものをとられた。金持は自分の家の息子を賢いと賞めたが、同じことをいった隣人を疑った。二人とも同じことを言いながら疑われるばかりでなく、場合によると殺されかねない。これを見てもわかるように、知ることは必ずしもむずかしくない。知っていることをいかに処理するかがむずかしいのである」(説難)
だいたい、まだたいして信用されてもいないのに、秘策を打ち明ければ、事が成功しても忘れられるが、過失があればたちまち疑われる。他の重臣に過失がある場合、たとえ礼儀正しく真実を述べても、逆に自分にはね返ってくる。また他の重臣の献策を自分が知っている場合も、他人の功績を盗もうとしているのではないかと思われる。さらに相手に不可能なことを強いたり、やめようと思ってもやめられないことをやめさせようとすれば、これも自分の身に危険が及ぶ。
また、相手と偉い人の話をすれば、間接に自分をあてこすっているのだと思われるし、バカなやつの話をすれば、自分を売り込もうとしているのだなと、思われる。相手の気に入る話をすれば、なにか欲しがっているのだな、と邪推されるし、相手のきらいな話をすれば、自分を試そうとしているのだな、と疑われる。簡潔にしゃべればバカだと思われ、詳細に述べれば、クドいと言われる。意のあるところだけ述べれば、卑怯と思われ、遠慮なく述べれば、粗野だとあなどられる。まことに人を説得することは容易なことではない。
「竜という動物はおとなしい動物で、これを飼いならせば、上手に乗り回すことができる。けれどもその喉の下に一尺ばかり鱗が逆生しているところがある。もしこれに触れると竜はたちまち逆上して人を殺す。君主にもまた逆鱗があるから、これを説得しようとする者は、逆鱗に触れないように注意しなければならない」(説難)
このため、真に有能なる人物でもその言が容れられるまでには、まわりくどい道をたどらねばならなかった。
「むかし、殷の湯王は理想的な君主で、その補佐役伊尹(いいん)は名大臣であった。その伊尹が湯王に説くこと七十回に及んだけれども聞き入れられなかった。やむをえず伊尹は包丁を握って王の料理人になり、湯王に近づき、ようやくその人柄を知ってもらったのである」(難言)
これは目的があってやることであるから、有能の士の恥とする行為ではない。料理人だろうが、太鼓持ちだろうが、究極の目的さえ達することができれば、それでよいと韓非は考えたのである。
|