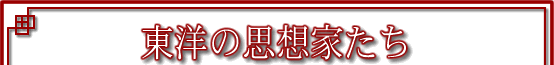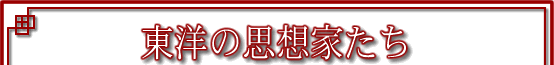|
「人もしなんじの右の類を打たば」という仮問に対して「左の頬をも打たせよ」と答えたのはキリストであるが、ではキリストの教えを奉ずる者がみなそのとおりに実行しているかというと、おそらくは反対であろう。右の頬を打つにまかせれば、左の頬を打つ手をさしひかえるとはかぎらないからである。ミュンヘン会談でチェンバレン英首相がヒトラーに譲らなければ、ヨーロッパの惨劇はあんなに拡大されないですんだかもしれない。一歩を譲ることはやがて百歩を譲ることになりかねないのが人間の世の中である。
東洋の思想家のなかで「以徳報怨」を主張したのは、わずかに墨家の一派をなす宋栄子だけであるが、今日その名を記憶にとどめている人もいないくらい、この考え方は中国人のあいだに人気がない。仁義を説いた孔子でさえも「以正報怨」という、はなはだ融通性に富む表現をもってこれに答えている。人間はほんらい私利私欲の徒であると考えている韓非にいたっては、敵味方の区別はいっそうはっきりしている。
韓非は韓の公子として生まれ、最初から特権階級であったから、おそらく生活にも困らなかったろうし、他の「文化人」たちのように諸国を遊説して売り込み合戦をやる必要もなかったであろう。しかし口に「仁義」を唱える連中が政府の重臣たちに取り入り、徒党を組み、議論いよいよ多くして国いよいよ弱体化するのを見ると、黙ってはおられなかった。彼は自分を世の「文化人」と区別する必要を痛感し、また徒党を組む連中ととうていいっしょになれないことを悟った。今日、韓非の代表的な文章として知られている「孤憤」は、こうした精神状態のもとで書かれたものである。全章を通じて人を動かすものありとすれば、それは道徳の荒廃に対する嘆きではなくて、私利私欲の徒に対するあふれるような怒りなのである。
「知術の士は必ず遠くまで見通すことができ、観察が明確である。観察が明確でなければ私曲を見破ることができない。法術をよくする者は必ず意志が強くて勁直である。勁直でなければ姦悪に対処することができないからである。こういう人は法に従って政治を行なう。これに反して一般に重臣と考えられている連中は法令を無視して私利を追求し、国家の財政を消耗して自分の便宜をはかり、その勢力は君主をしのぐばかりである」(孤憤)
もし知術の士が用いられれば、重臣どもの心中を見通し、彼らの姦悪を封じることができる。かくて実際に国のためになる人間はおとしいれられる危険性がなくなる。つまり法術の士と、顔にものをいわせる当路の重臣は、もともと両立できない仇敵同士なのである。
いまの重臣は勢力をもっているから内も外もそのために協力してくれる。君主さえも彼らに頼らなければ動きがとれない。だから外国人でさえも君主をバカにして重臣を尊重する。役人も彼らににらまれたら仕事ができないから進んで下僕となるし、侍従官も彼らの反感を買えば君主に近づけなくなるから、彼らの悪事を隠そうとするし、また学者も彼らのごきげんをとらなければ、なかなか重用されないから、彼らに都合のよい論説をなす。
この四者を資本として、重臣は、法術の士を除き、この四者に取り囲まれて君主は彼らの善悪さえつかない。かくて、重臣の権勢はいよいよ重く、君主の権勢はいよいよ地に落ちる。
「君主のまわりには必ずお気に入りの者が集まる。彼らは故老に近づき、そのやり方をまねる。このように、君主と側近が好ききらいまで同じというのは、もとより出世のためである。官爵の重い者は徒党も多く、国じゅうをあげてその功徳を賞め賛える。ところが法治主義者は、君主のやり方に、干渉することこそあれ、君主に気に入られているわけでもなければ、重臣のあいだに勢力をもっているわけでもない。むしろ法を楯にとって君主の過失を改めさせようとするのであるから、君主の感情と相反発する。勢力がなく、徒党を組まず、孤立無援、しかもそれでお気に入りの連中と争うのであるから衆寡敵せず、いってみれば、口ひとつで一国を相手に争うようなものである」(孤憤)
国の利益と個人の利益は元来相反するものである。君主の立場からいえば、有能な者を起用したいが、起用される側からいえば、能も功もなくて目的を達するにこしたことはない。そこで勢力のある者に取り入り、徒党を組み、利権をもらったり、公金を横領したりして、国家はいっこう繁栄しないのに、大臣の懐ぐあいばかりよくなるような事態が起こる。
「亡国の君主は国をもっていないわけではない。国はあってもそれを自分がもっていないからである。ことに弱小国の場合は、大臣が外国と通じその力を借りて自国で勢力を張ろうとする。大国と結ぶのは自国の滅亡を防ぐためであるが、その結果は大国と結ばない場合よりも滅亡を早くするものである。それゆえ、大臣を信用しないほうがいい。信用されていないとわかれば、大臣が国を売るようなことが起こるはずはないのである」(八姦)
ところが、現実はどうであろうか。君主は証拠固めもしないで人を殺し、功績を見もしないで人を任ずる。君主の周囲には悪党がうようよしていて袂をあげて待っている。もし賄賂が思いどおりに入ってこなければ、たちまち風向きが変わって、昨日までの賛辞が今日は悪口になってしまう。これでは真の知士が死をおかしてまで進言に及ぶことがどうしてできようか。「おれはあのトラどもを愛したりするものか」と韓非は思ったにちがいない。「おれがかりに政権をとったら、やつらをみな、檻の中に入れてしまう。キリストのお説教を聞くのは、それからでもおそくない」
|