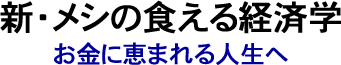|
第1回
まえがき
いまから十六年前の1984年に、
私の金銭についてのエッセイを集大成した形で、
『メシの食える経済学』と題した本の出版が
グラフ社で企画されたことがあった。
「このタイトルだけで十万部ですね」
とさる書籍販売会社の担当重役さんから誉められたそうだが、
はたして出版されると
すぐベストセラーズの仲間入りをしただけでなく、
ロングセラーズとして長く版を重ねた。
経済学の本は毎年おびただしい数が出版されるけれども、
この本を読んだら、お金儲けのヒントになり、
メシが食えるようになる内容のものは
滅多にないということであろう。
私は天下国家の経済に無関心というわけではないが、
お金の話をするなら、自分のポケツトの一万円札が
ポケットから出て行ったら、
どこをどう遍歴して子や孫まで連れて帰ってくれるのか、
それとも他人の家に行ったっきり戻って来なくなるのか、
それを自分はどういう形にしたいのか、
そのためにはどうしたらいいのか、
なるべく身近な話からスタートした方がいいと思った。
そのために貯金の仕方から株のやり方、
はては、不動産の買い方、節税の仕方に至るまで、
自分の失敗談も含めてさまざまの角度から執筆を試みた。
私は頭の中で考えるだけでなく、
必ず実証をしないと気がすまない質なので、
さんざ失敗もしたが、うまく行った例もあったので、
差し引き多少の財をなすことができた。
しかし、それは人から評価されるよりは、
嫉妬を招くことであったから、
文化的に世の中に貢献してくれましたねと認められたことは
あまりない。
従って新聞や雑誌の書評欄には
ほとんど取り上げられなかったけれど、
常々甲子園いっぱいの観衆よりは多くの読者に恵まれたので、
全く酬いられなかったというわけでもなかった。
幸か不幸か、お金には古今東西を通じて
不変の真理という面もあるが、
時代と共にその扱い方を変えないとつきあいきれない面もある。
成長経済が続いていた時代に
これこそ不変の哲理と思っていたことでも、
成熟社会に入るとそのままでは通用しないことも
数々見られるようになった。
たとえば土地神話は大きく崩れたし、
財産三分法の中で、株の出番が
かつて考えられなかった形ではじまろうとしている。
『メシの食える経済学』も20年近くたってみると、
そのままでは「メシの食えない経済学」
に堕ちかねないところまで来てしまった。
私自身、バブルがはじけたあと次々と自分の考え方に修正を加え、
時代に対する私なりの新しい対処の仕方もやるようになった。
社会全体が老齢化しているし、
産業界全体が急激な勢いでグローバル化の道をたどっている。
こういう時代にはこうした変化にふさわしい心構えと
配慮がなければ、事業経営も財産づくりもできなくなっている。
そういう必要を痛感しているところへ、
グラフ社から再版の話があったので、
いっそこの際、2000年代に波長のあった
「新・メシの食える経済学」に
全面的にやりなおしてみてはどうかという提案をした。
できあがったものを見ると、
タイトルは同じでも内容はほとんど一新してしまっている。
さすがにお金は生き物だけあって、
環境が違うと生き方もまるっきり違ってしまっている。
お金のそうした新時代の生き方が
皆さんのご参考になればと心ひそかに願っている。
2000年10月吉日
中国四川省九塞溝にて 邱 永漢
|