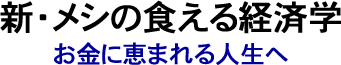|
第2回
日本人のお金の扱い方には特徴がある
「経済学」はお金の動きを社会現象としてとらえようとするが、
「文学」は同じ動きを人の心の屈折からとらえようとする。
私は「経済学」を学問として教わったが、
たまたま職業として「文学」に従事したので、
お金をテーマにするとすれば、
やはり「お金と人間」という接近の仕方になってしまう。
だから私が書いた一冊目のお金の本は『婦人公論』誌に連載した
『金銭読本』であり、
当時、単行本にまとめて中央公論社から出版したが、
中公文庫から文庫本として発行されている。
『金銭読本』のまえがきで、
私は清の乾隆帝が福建の港町に行幸したときのエピソードを
引き合いに出している。
海にいっぱい浮かんだ船を見て
「ずいぶんいっぱい船があるなあ」と
乾隆帝が感嘆の声をあげた。
すると、おつきの者が
「陛下、たくさん浮かんでいるように見えても船は二隻だけです。
一隻は富貴、もう一隻は名声と申します」と奏上したという。
これは、もちろん、おハナシであろうが、
人々が一生を通じて努力する目標が「お金持ちになること」と
「名声を博して他人から尊敬されたり、
チヤホヤされたりすること」であるという点では、
昔も今も変わりはない。
とすれば、お金に関する学問は、
お金の動きを現象としてとらえるよりも、
お金持ちになろうと心がける人々の心象に
立ち入る方がより実際的であり、より親近感がある。
そうした目で見ていると、
私が中国人と日本人の混住した
台湾という社会で育ったせいもあるが、
日本人の金銭観というか、日本人の金銭に対する態度というか、
とにかく日本人のお金の扱い方に
かなり特徴があることがやたら目につくようになった。
たとえば、日本人はお金のことをあまり口にしない。
文士の人が原稿を頼まれる場合でも、
どういうテーマについて
何枚の原稿を何月何日までに書いてくれと依頼されるが、
依頼する方も依頼される側も、
稿料はいくらかということは一切、ロに出さない。
じゃあ稿料のことは気にしないかというと、
稿料をもらってから安すぎるといって
ブツブツ文句を言ったりする。
それくらいなら「先小人、後君子」
(はじめは小人のごとく振舞い、
あとは君子になって文句は言わない)の方がよいと思うが、
日本人はなかなかそこまでは徹底できない。
どこかの会社に新しく就職をする場合でも、
入社試験を受けに行ったり、面接に行ったりするが、
「私のサラリーはいくらですか?」
と聞くフレッシュマンはまずいない。
もちろん、どこの会社でも会社案内のパンフレットには
初任給二十万円などと書かれている。
しかし、社会保険や健康保険や組合費を引かれたら、
手取りでいくらになるのか、住宅手当はあるのかないのか、
家族手当はどうなっているのか、
詳細はわからないし、それを根掘り葉掘り聞く人もいない。
給与をいくらにするかは、会社に規定があるし、
会社は悪いようにはしないはずだし、
あんまり聞きただしたりすると、
がめつい奴だと上役の心証を悪くするだろうと
遠慮するからである。
ことに一番ひどいのは、
飲み屋の勘定を払うときであろう。
「お愛想」というと、
小さな紙に総額だけ書いた紙切れを突き出してくる。
一体、ビールが一本いくらなのか、水割りが一杯いくらなのか、
またあのピーナツとチーズが一皿いくらなのか、
どこにも何にも書いていない。
どう足し合わせても、それだけの金額にはならないと思うのだが、
別にそれを聞きただすでもなく、
おとなしく財布の底をはたいてしまうのである。
|