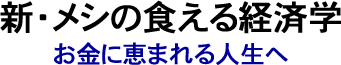|
第16回
財産の「財」という字は、お金についての才能のこと
世の中には自分一人でできる仕事と、
多くの人の協力を得ないとできない仕事とがある。
作家とか、画家とか、発明家は一人でやれる仕事であろう。
俳優やスポーツ選手や映画監督は、
個人の才能がものをいう職業であるが、
その才能を存分に発揮するためには
チーム・ワークを必要とする。
しかし、その人がいなければ成り立たない仕事であるから、
人気が出れば、一人で百人分もギャラを稼ぐことができる。
千両役者といって、その人の人気だけで、
多くの人々を養っていける人は
いつの時代でも必ずいるものである。
私は物を書く仕事を何十年もやってきたので、
チーム・ワークということがあまり念頭になかった。
自分一人で考えて、自分一人で作業をし、
自分一人で稼ぐことができたせいもあろう。
しかし、自分一人で「仕入れ」から
「生産」「販売」までできたといっても、
仕入れ先もあれば、販売先もあり、
それぞれの相手に理解され、支持され、
協力してもらわなければやっていけない。
いくら商品をつくっても、
売れなければお金にならないことは、
他の商売と同じだが、
商品づくりが一人でできるということが
電気製品をつくったりするのとは違う。
そういった自由業に従事する人はいくらもいるが、
いずれも個人的才能に頼る面が強いので、
職人気質とか、名人気質といった気難しさが伴い、
わがままだったり、性格破綻が目立ったりする。
そういう人でも、 人が喜んでお金を払ってくれるのは、
俳優さんや音楽家やスポーツ選手なら、
観客を楽しませる能力があるからだし、
陶芸家や彫刻家や画家なら、
他に抜きん出た作品をつくり出してくれるからである。
私の見るところでは、そういう才能のある人で、
人格円満な人はあまり多くない。
どうしてかというと、一芸に秀でた人は
性格的にバランスのとれた人は少なく、
一人の人間の才能がある一点に
過剰に集中された結果であることが多いからである。
だから、藤山寛美とか、勝新太郎とか、
あれだけ観客を酔わせ、
あれだけザクザクとお金が入ってくるのに、
高利貸に追いまくられて、
お金と駆けっくらをする生活にさらされたりする。
ただ、そうなったらそうなったで、
腹をくくり、世間の常識など糞食らえ、
とばかりに、無頼というか、身勝手というか、
自己流の生き方ができるようになるという一面もあるのである。
そういった人々の脱線した生活ぶりを見て、
一般の人がそれを見習おうと思ってもそうはいかない。
サラリーマンになれば、
サラリーマンの社会を支配するルールがあるし、
独立自営をすれば、
独立自営者が守らなければならないルールがある。
事業と名のつくものになると、
たとえ従業員が二人か三人しかいない企業でも、
会社となればチーム・ワークが必要になる。
ましてそれが何百人、何千人、
更には何万人という組織になると、
ルールも必要なら、信頼関係も不可欠で、
人間と人間の関係がうまくいかない企業は、
効率もあがらないし、お金も思うように儲からない。
人間、ある程度財産を持ってみると、
家や土地が財産ではなくて、
それをつくり出す才能が財産であることに気づくだろうし、
人を使ってみると、人はお金を生み出すための手足ではなくて、
人材そのものが財産であることに気づかざるを得なくなる。
したがって財産の形になっていて、
誰にでもそれとわかる土地や家や株は
それほど重要なものではない。
仮にそれを全部なくしてしまうようなことが起こっても、
それをつくり出す能力と人材を持っておれば、
すぐにまた取り戻すことができるからである。
石橋正二郎とか、松下幸之助とかいった人たちは
敗戦によって、戦前に築いた財産をいっぺん失ってしまった。
しかし、本人の才能は頭の中に保存されていて無事だったから、
残党を集め、
新しく傘下に入ってきた人々を働かせることによって、
戦前よりずっと大きな財産を再び築くことができた。
財産の「財」という字は、
貝(お金)についての才能のことであって、
お金そのもののことではない。
だからそうした才能を身につけることが
お金そのものよりも大切である。
金持ちの二世を見ればすぐにもわかることだが、
いくら親から莫大な財産を継いでも、
お金を運用する才能に恵まれなければ、
あッという間に霧散してしまうものなのである。
|