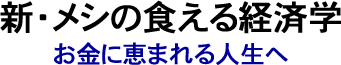|
第24回
日本で「仕事を選ぶ」とは、会社に入ること
人が自分をしあわせと感ずる条件は、
人によってそれぞれ違いがあろうが、
万人に共通なものは仕事と家庭であろう。
封建時代には職業選択の自由がなかったから、
百姓の俸は百姓になり、商人の倅は商人になった。
家族は家業を手伝い、長男が家を継いだ。
しかし、そういう時代にも、農家の二男、
三男は耕す土地が与えられなかったから、
丁稚小僧として商家に奉公し、
やがてノレンを分けてもらって独立する道がひらけていた。
そういう小僧が番頭になり、
利発で勤勉なところを買われて婿養子に迎えられるのも
珍しくなかった。
恐らくその反対のコースをたどって
サムライや町人から帰農する人もあっただろうから、
封建時代にも、
目立たない程度の職の入れ替わりはあったに違いない。
こうした入れ替わりは、いつも人々の運命を大きく変えた。
わけても戦乱の世の中になると、
貧農の中から身を起して天下取りになる者もあれば、
豪商になる者も現われた。
明治以降、職業が自由に選べるようになると、
家業を捨てて勤め人になる者が増え、
遂にサラリーマンが個人営業者や
自由業者を超えて人ロの圧倒的多数を占めるようになった。
学校を卒業して社会に出るということは、
日本では会社に就職することであり、
学校を卒業すると同時に独立経営する人は滅多にいない。
したがって「仕事を選ぶ」とは、
どんな会社を選ぶかということにほかならず、
それがその人の一生を決めてしまうことになった。
しかし、こうしたしきたりはどこの国にもあるわけではない。
たとえば、台湾や香港では、
学校を出たら一応は就職する人が多いけれども、
それでその人の一生の仕事が決まる性質のものではない。
同じ会社に一生勤める場合も皆無ではないが、
見込みがないとわかれば、すぐにも辞めてしまうし、
反対に仕事として将来性があると思えば、
ひととおり仕事を覚えたところで会社を辞めて独立をしてしまう。
中国人にとって就職とは、(1)仕事を覚えるため、
(2)それを探しあてるための一時的な腰掛け、
のどちらかであって、(3)生活の糧を得るため、
というのは二の次、三の次といってよいだろう。
そういった意味では、
どんな業種の会社に勤めたかは
本人の将来を大きく左右するけれど、
どの会社であったかはそれほど大きな意味を持たない。
日本人の就職が実質的に「就社」であるのに対して、
中国人の場合は文字どおりの「就職」であるから、
自分に向いた職であっても仕事を覚えたら、
他に動くか独立することが考えられるし、
自分に向かないことがわかればすぐにも転職をするから、
自分の一生をーつの会社に託することはほとんどない。
いまの中国人にとっては、どこの会社に就職するかよりも、
ある程度の修業をしたあとに独立してどんな仕事を選ぶかが、
その人の運命を大きく左右する。
たとえば、共産党治下の中国大陸では、
転職の機会はきわめて少なかった。
ある職場から解雇されようものなら、
そのまま失職する心配があったから、
老いも若きも与えられた職業にしがみついてきた。
サラリーはつい最近まで月に百元とか、百五十元にすぎず、
かなり改善された今日でも、三百元、四百元あれば
上々の方に属する。
いまの為替レートで換算すれば、
せいぜい五千円に届くかどうか程度の金額だから、
いくら住居費や食費が安いといっても、
豊かさの感覚からはほど遠い。
そういう生活に耐えてきた人々が、
最近の開放政策のさなかで続々と脱サラを試みるようになった。
|