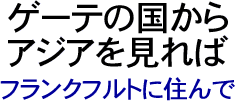|
第250回
ヒバリがさえずる小道から
2006年11月からの長きに渡り、
このコラムを続けさせていただきました。
読者の皆様、本当にどうもありがとうございます。
そして、執筆の機会をくださいました邱先生、
粘り強く伴走いただきました編集部の皆様にも
心からお礼申し上げます。
このコラムの執筆は、まるで南ドイツにある、
牧場の散歩道を歩むような素晴らしさでした。
遠くには、雪を頂くアルプスの山々が見え、
お日様がぽかぽか当たり、野花が咲き、
ヒバリが空高くさえずる素敵な小道です。
見えるものを1つずつゆっくり観察しては
絵葉書にしたためるような楽しみがありました。
私のドイツ暮らしへの「崖のぼり」に費やした年月は、
どのようにすれば、欧州で通用する生き方ができるのか、
私自身の「目線」の据え方というより、
むしろ「度胸」の据え方を模索した時間でした。
もしも、欧州暮らし1番目のポイント
「差別されたと思うな、相手はわからないと思え」を
自分のものにしていなければ、今なお5番目のポイント
「欧州の結論は、(0・1)×(0・1)」には
気が付いていなかったことでしょう。
1番目のポイントは、私の宿題「中国古道具」の
ご縁の中で得た、貴重なアドバイスでした。
欧州は、日本人が想像する以上に強烈な格差社会です。
欧州人の間に限った激しい偏見が
現存するかもしれません。
一方、アジア人は今や、欧州で
たっぷりお買い物してくれる大得意様です。
アジア人を激しく差別する暇なぞ、一般欧州人にはありません。
「欧州人に差別されたのでは?」という言葉を
あまりにも気軽に使いすぎると、
見えるものも見えなくなってしまいそうです。
日本人も勇気を出して、ぐっと踏み留まり、
自分の目でよく確かめ、自分1人の頭で考えながら、
欧州や日本の周りの国々を見られるようになったら
素晴らしいだろうな、と思います。
では、私も新たな勇気を持って歩みを進めましょう。
ドイツ語で、気軽な「じゃあ、またね!」の
ご挨拶には、こちらをよく使います。
チュ〜ス(Tschues)!
|