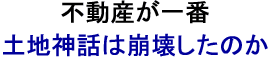|
第68回
土地問題の抜本的解決策
今次の値上がりの例を見てもわかるように
土地があがりそうかどうかは私たちでもあるていどの予測がつく。
あがりはじめたら、
二、三年はそれが続くから、
あがりはじめるハナに暴騰防止策を打ち出せば、
いくらか効果が期待できる。
ただし、それは罰金的税金をかけることではない。
罰則を設けるよりも、供給をふやすことを優先すべきで、
土地の供給を妨げているようなあらゆる規定を緩和したり
廃止したりすることからはじめるべきである。
たとえば東京には日本国中から人が集まってくる。
東京及びその周辺の土地があがるのも
そうした人口の集中があるからである。
しかし、だからと言って東京に集まってくる人たちに
禁足令をしくわけには行かないであろう。
人には移動の自由があるし、人が都会地に集中してくるのは、
メシのタネが都会にころがっていて、
都会に出てさえくれば、職にありつき、
何とか食って行けるようになるからである。
したがって東京への人口集中を防ごうと思えば、
大学のような都心部におく必要のない機関は、
特別の免除措置や奨励策をとって周辺都市に移転させるとか、
あるいは、政府機関そのものを郊外に移してしまえばよい。
しかし、政府機関を移したりすると、
ブラジリアとか、ワシントンとか、ボンのように、
政府の許可をとりに行くために
時間と人の浪費が生ずるだけだから、
必ずしも人口の分散にはならないかも知れない。
むしろ狭い土地に人口が集中する傾向を前提とした
積極策をとったほうが効果的で、
いまの東京なら、(1)建ぺい率を思い切って緩和する、
(2)日照権や道路制限は全廃する、
(3)農地の宅地転換に優遇措置をとり、
農地として残す者には宅地並み課税をする、
(4)鉄道その他公共的施設の敷地の上に建築を許可する、
と言った抜木的政策をとれば、
住宅や店舗や事務所の供給が爆発的にふえるから、
マンションの値段や賃料が下がることは、
まず間違いないであろう。
さき頃、アメリカで世界の大富豪の番付が発表されたが、
その第一位に西武の堤義明、
第二位に森ビルの森泰吉郎、
第三位に秀和の小林茂といった人々の名前があげられた。
いずれも日本で有数の不動産業者であり、
東京及び周辺の土地の暴騰によって
財産価値の上がった人たちばかりである。
そういう人たちが日本の工業を促進して
日本の国に富をもたらした人々より
金持ちにランクされることは
決して褒めたことではないのであって、
現に東京の土地が世界一高くなったために、
まともな人たちが家一軒新しく東京に持つことさえ
容易でなくなってしまっている。
私は、企業や個人が自衛策として
不動産を持つことをすすめてきたが、
東京で働くサラリーマンたちが
一生稼いだお金で東京に
二十坪のマンションー軒買えないような社会が
良い社会だとは思っていない。
一体、 政治家たちは何をしてきたのだろうか、
とあきれるほど政治は貧困な状態に放置されている。
どうしてこういうことになったかと言うと、
日本の政治家は、お金のかからない政策には
ほとんど興味を示さないからである。
日本の選挙制度はお金がかかりすぎる。
国会議員であり続けるためには選挙のたびに
五億円も十億円もお金がかかると言われている。
この資金を捻出するためには
選挙民に絶えず恩を売っておかなければならない。
議員さんのかなり多くの人たちが
建設業者に援助してもらっているのを見てもわかる。
それは建設業とその関連企業に従業員が多いというだけではない。
政府の建設予算が見返りになっているからで、
予算のぶんどり合戦に身を挺して
「これだけの仕事をとってやったんだから
選挙の時はたのむぞ」といえば業者に対して威力があるが、
「建ぺい率を緩和してやったぞ」と言ったのでは、
議員さん個人の功績にはならない。
実際にお金の動く法案でないと、
議員さんたちが関心を示さないのは、
日本の政治のシステムから生じた欠陥というべきであろう。
おかげで誰が総理大臣になっても、
建ぺい率を緩和しようという具体的な動きにはなりそうもない。
もし東京の環八の中の建ぺい率を今の三倍に緩和したとすれば、
それだけで一千万人の人ロが
すっぽり収容されてしまうだろう。
むろん、そのためには、再開発に対して、
いろいろと条件をつけなければならないだろう。
たとえば、一ブロックの大きさは
少なくとも三百坪以上でないと駄目だとか、
ブロック内で90%以上の所得者が賛成しているのに、
反対者があって解決できない場合は強制収容ができるとか、
二階建て以下の家に住んでいる人の税金は
その上に建てられる可能性のある建築面積分負担してもらうとか、
反対に、資金の足りない者には
低利の長期資金を貸すとか、
相統に際して相続税の減免をするとか、
要するに鞭とアメを兼ね備えた奨励策が必要であろう。
|