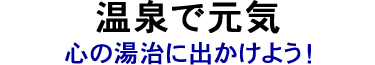| 第49回
消える自然湧出温泉
東京電力福島第一原発事故を受けて、
日本の電力を支える自然エネルギーとして
地熱発電への期待が高まっています。
火山の多い日本は、世界有数の地熱資源国。
また風力や太陽光のように天候に影響されない点も、
地熱発電が期待されている理由です。
地熱発電は、地中に井戸を掘って高温の蒸気を取り出し、
その蒸気によりタービンを回す仕組みです。
しかし資源の約8割は
開発が規制されている国立・国定公園の下にあるため、
これまで日本では、あまり活用されていませんでした。
そこで開発されたのが、
井戸を公園の外から斜めに掘る技術です。
これならば公園内にある資源でも、活用することができます。
しかし、これに警鐘を鳴らす人たちがいます。
群馬県温泉協会長の岡村興太郎氏は、平成24年1月発行の
「群馬県温泉協会誌」に次のようなコメントを寄せています。
<新規の温泉開発も掘削技術の進歩とともに、他の影響も加わり、
まず自然湧出の温泉は、温度・湧出量・含有成分等の減少を経て、
湧出が止まり、あるいは枯渇化に向かう傾向が多い。
温泉は未知の分野が多く、地下の構造や湧出構造の解明、
温泉のモニタリングが急がれるゆえんである。
また一度、地熱発電が開始されると、一定量の蒸気確保のために、
2〜5年に1本の割で還元井戸を掘削し続けることが解っている。
際限のない、無秩序な開発にならないよう、
最初から充分に検討されるべきである>
さらに氏は、明治25年に発刊された群馬県の温泉分析書
「上野鉱泉誌」に記載されている74ヶ所の温泉地に触れ、
<現存する温泉は30ヶ所余りとなっている。
昭和30年代以降の温泉掘削技術の進歩で、
昔ながらの自然湧出の温泉が消えてしまった>
と、これ以上温泉を掘削し続けることへ懸念を抱いています。
この120年の間に、群馬県内から
40ヶ所以上の自然湧出温泉が消えたことになります。
また、掘削による温泉は増えているものの、
県内の温泉の総湧出量は年々減少していることも事実です。
特に自然湧出温泉の湯量の減少は顕著で、
ピーク時の約30パーセントも減っています。
以上の数字を踏まえた上で、地熱発電の開発に限らず、
温泉の掘削という行為自体を見直してほしいものです。
|