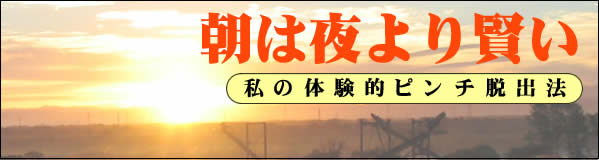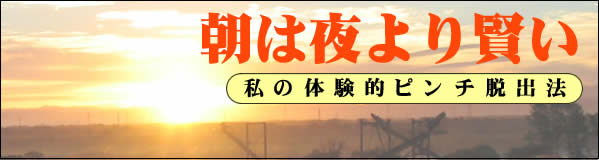18. 消費者心理を読み間違えるな
不況だから売れないのか?
商売がうまく行かない原因は、つき詰めて行けば、たいてい自分自身に責任の大半がある。
しかし、人間は誰でも自分の欠点は認めたがらないから、責任の転嫁をする理由を考える。最近でいえば、「不況」が一番恰好の口実になる。
「商売はどうですか?」
「いやあ、この不況ですからねえ」
とハンで押したような返事がかえってくる。不況になれば消費がおちるから、売れていたものも売れなくなる。売れなくなったのを不況のせいにすれば、一応の説明はつく。
では、不況から立ち直ったら、売れなくなったものが再び売れるようになるのだろうか。たとえば、街に新しくスーパーができて、お客はこちらの店の前を素通りして向こうにばかり買物に行くようになったが、景気が恢復したら、それらのお客さんはまた戻ってきてくれるのだろうか。誰にきいても、答えはノーであろう。商店街のお客がスーパーへ移ったのは、マスプロ、マスセールの時流に乗って、消費者のニーズにこたえた商売をスーパーがやるようになったからであって、「構造変化」という言葉で表現される性質のものである。スーパーそのものが小売店であり、資本があるから大型店になったのではなくて、消費者の要求に沿った経営をやったから大型店になったのである。経営者の出身を辿っても、もとは小さな商店の持主にすぎなかった人たちである。
一方、商売のうまく行かなくなった商店主には被害者意識が強くて、自己反省はあまりないから、大資本にしてやられたと思っている人が多い。
しかし、時世が変わるとそれについて行けない企業は、スケールの大小にかかわらず、同じように被害を受ける。たとえば、豊かな社会になって物離れが激しくなると、物が売れなくなるのは商店街の小売屋だけではない。スーパーもデパートも同じように売上げがおちる。とりわけ実用品は、すでに飽和状態に近づいているせいもあって、売上げがなかなか伸びないから、主として実用品を扱っているスーパーの衣料品売場はまともにその直撃を受けるし、デパートの売場の中でも実用衣料品を扱っている部門は減収減益に悩まされる。こういう現象の中には、
(一)季節的要因、たとえば冷夏、あるいは暖冬のせいで売れるべきものが売れなかった、
(二)三年か四年周期でくり返される不況期にちょうどぶつかっている、
(三)流行の変化、
といった偶然から生じたマイナス要困も当然考えられる。
|