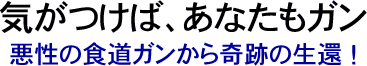|
第1862回
子宮頸ガン・円錐切除手術後の大出血
いま発売中の「いのちの手帖」第4号の20ページ巻頭対談=
逸見晴恵さん VS イディス・シーさんによる
「●ときめき対談● 子宮ガン、乳ガンを超えて――
もっと、わくわく、 もっと、輝いて・・・
〜この10年は”生きがい探し”の旅でした〜」
内容紹介の続きです。
「夫・逸見政孝の悲しみを乗り越えて14年」という項目に続いて、
イディス・シーさんの10年にわたる
乳ガン、子宮ガンの秘話が「子宮頸ガン・円錐
切除手術後の大出血」という章で詳しく明かされます。
*
司会:イディス・シーさんの場合も、
子宮頸ガンで円錐切除なさったと、まえに伺いました。
「いのちの手帖」の第2号にも闘病記を寄稿していただきました。
その時の医師や病院の選択のようすを
もう少し詳しくお聞かせください。
医師との間で困ったことはありませんでしたか?
シー:私の場合は、大出血という症状から始まって、
出血してからものすごく体がだるくておかしいなと思ったんです。
あまり具合が悪いので、
検査した結果が子宮頸ガンだったのです。
逸見:自覚症状があったケースですね。
シー:私は、アメリカのロサンゼルスと台北に家があるのですが、
子宮頸ガンが発見されたのはアメリカです。
医師からは、
すぐに子宮の手術しなければダメだと言われたんですが、
自分をよく知っている台湾の医師にも相談したら、
全摘出する必要はないだろう、
ガンの部分だけの円錐切除でいいだろうというアドバイス受け、
それによって手術を受ける決心をしました。
逸見:じゃ、いい先生に出会ったわけですね。
シー:アメリカに戻って、
さらにセカンドオピニオンを求めて、
複数の医師の話を聞き、
最終的には全摘出手術はしないという判断を下しました。
逸見:周りの人たちがよかったですね。
司会:逸見さんの場合は早期検診が、
イディス・シーさんの場合は用意周到な
セカンドオピニオンが、
ガンに克つポイントというわけですね。
逸見:さっきもいいましたが、
子宮ガンの検診は、面倒がったり、
恥ずかしがったりせずに、必ず受けた方がいいですよ。
シー:私としては、自分が納得のいくまで
慎重に手術を選んだつもりでしたが、
退院して一ヶ月ほどして、
とんでもないハプニングに見舞われたのです。
手術痕から血が止まらなくて大出血したのです。
逸見:じつは私も大出血したんですよ。
円錐切除って、かなり深く切り取るんです。
先年、亡くなられた土屋繁裕先生にも
相談したことがあるのですが、
外科医がちゃんと縫っていなかったのだろうって、
おっしゃっていました。
二人ともそうなんですから執刀医の技量も問題ですね。
しかし、そこまでは患者は分からない。
*
続きはまた明日。
詳しく読みたい方は「いのちの手帖」第4号をどうぞ。
お問い合わせ、購読希望の方は、別掲の購読の手引き=
◆季刊「いのちの手帖」及び
「ガン延命学 新書」の購読の手引き◆
にしたがって、ご連絡ください。詳細は
スローヘルス研究会編集部の方から返信いたします。
|