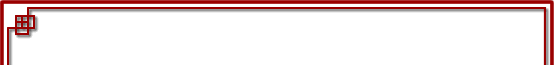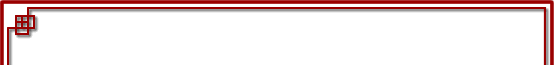人間社会の愚かさを小バカにした人間が、人間社会に名をとどめることは、考えてみれば、皮肉な現象である。「虎や豹は山中にあって怖いものなしの生活をしているが、しかも人間の罠にかかるのはみごとな皮を着ているからである。あの皮を脱ぎ捨ててしまいたい」と荘子は言った。ところが、皮を脱ぎ捨ててしまったはずの荘子が、死んで名をのこしたのは「皮を脱ぎ捨てる行為」そのことが、実はまた一種の皮であったことを証明している。とすれば、著述をしたことが荘子の最大の誤謬であるということになりそうである。ただ、荘子の荘子たる本領は、彼の履歴書を後世にのこさなかったことであろう。就職を潔しとしなかったのであるから、当然といえば当然であるが、そのために後世の考証学者は大いに不便を感じている。もっとも杳としてつかみどころがないことがかえって魅力的であり、それだけ荘子株を高からしめている原因となっていることも事実であろう。
今日わかっていることは、彼が荘周という名前の男で、西暦紀元前四世紀ごろ、中国の歴史上でいえば、戦国時代に、宋の国の蒙というところに生まれたらしいこと、妻があったらしいこと、人に使われるのがきらいで、ちょっとしたサラリーマンになったが、長続きしなかったらしいこと、ぐらいなものである。もうそうだとしたら、彼の著作とされている『荘子』三十三篇のなかには、たとえば「説剣第三十」のように、それに遅れること三百余年の時代の話が出てくるから、『荘子』三十三篇とは、『荘子』という主流に「荘子的」な支流が長い歳月のあいだに合流して、一つの大河になったものと見なければなるまい。
そのなかでどれが荘子の真作であり、どれが後人の偽作であるか、を見分けることはたいへんな仕事である。当然、解釈も異なり、議論も百出する。しかし、荘子自身、人間のそうした努力を嘲笑している以上、荘子を語って荘子に笑われるようではしかたがないであろう。だから、そうした仕事は考証学者、傍註学者に任せておいて、われわれは荘子のものの考え方に直接あたってみることにしよう。
実際間題としても、「荘子的」なものの考え方が重要なのであるから、荘子がいかなる人物であったかは、いわばどうでもよいことである。彼が楚の威王から宰相に迎えられようとしたとき、その使いに向かって、「あなたはお祭りのときに犠牲にされる牛を見たことがあるでしょう。刺繍をした衣を着せ、草や豆をぞんぶんに食べさせます。しかし、いったん、大廟の中に引かれて行って供物にされるときは、一疋(ぴき)の子牛に帰りたいと思ってももうできないでしょう」(列禦寇第三十二)と言ってきっぱり断わったという話は有名である。
しかし、それよりも私の興味をそそるのは、彼が(今日のことばでいえば)前科者を愛し、好んで前科者の幸福について語ったことである。彼自身が前科者であったか、あるいは単に前科者の観察者にすぎなかったか、それは今日のわれわれにはわかろうスベもないが、人間関係を窮屈に規制する道徳や法律を小心翼々として墨守しているふつうの人間に比べれば、たしかに前科者は自由奔放な生活をしているように見える。少なくとも彼らは、人間社会に住んでいながら、全然別なルールないし哲学によって生活をしているように思われる。
『荘子』三十三篇のそもそものヒントが、案外そんなところに始まっているのではないか、とさえ私には想像されるが、いずれにしても理論的であろうと心がけるよりは、むしろ読者に、想像力ないし憶測の余地をありあまるほどのこしておこうというのが、荘子のネライであったかもしれない。荘子のロマンチシストたるゆえんであろう。
では荘子は、ミレトスのターレスのように空を見つめていて溝に落ちるような哲学者であっただろうか。荘子が空想の世界に遊ぶ夢想家であったことは疑いの余地がないが、同時にまたきわめて緻密な論理的頭脳の持主であったことは、彼の齊物論における議論の進め方をみれば一目瞭然である。これはもとより私の推測にすぎないが、かりに孔子、荘子、韓非子と三人並べて知能テストをやるならば、荘子が意外にも最も優秀なる成績をあげるのではなかろうか。また、もちろん、宰相のイスなど眼中になかったが、かりに宰相の地位に置かれたら、孔子などよりはるかに敏腕をうたわれる名宰相になっていたのではあるまいか。
なぜ、私がそう考えるかというと、私には今日のこされている荘子の思想は、着物にたとえるならば、ちょうど、裏地のようなものであり、彼は裏と表をことさらにひっくり返して着たとしか思えないからである。あれだけみごとな裏地がついているからには、表地は少なくともそれと調和する程度にりっぱなものだと考えるべきだし、それを惜しげもなくひっくり返して、裏地の柔らかいところだけをぞうさなく広げてみせるところに、荘子が見かけによらぬ硬骨漢であったことがわかるような気がする。さもなければ、宰相のイスが絶大な権力を意味したあの時代に、あたかも穴のあいたボロ靴のように捨てて顧みなかった気持が理解できないであろう。 |