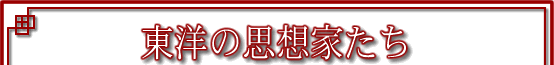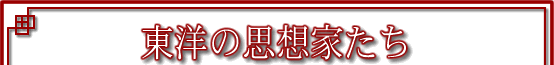常識の豊かな者でなければ、常識のいかなるものであるかはわからない。常識がいかなるものであるか、よくわからなければ、常識を打破することは不可能である。だから、よくこれを破るものは、よくこれを知るものというべきであろう。
荘子は既成概念のなんたるかを知っていた。だから、既成概念を打破するためには、似たような「ありうべきこと」をもってきてこれを甲論乙駁するよりも、「ありうべからざること」をもってきて、それが「ありうべからざること」であると証明できないことを示すことによって、逆に「ありうべきこと」が必ずしも絶対的なものでないことを立証しようとした。開巻第一ぺージから奇想天外、われわれ常識人を魂消させるような叙述をことさらに展開したのは、こうした理由によるものである。
「北海に鯤(こん)という名の大魚がいた。その大きさはとてつもないもので、何千里あるか測り知れない。変じて鳥となると、今度は鵬と呼ばれた。鵬の背中だけでも何千里という幅があり、怒って飛び上がると、その翼は天に垂れさがった雲と見まがうばかりである。海がざわめくとき、この鳥は南海へ向かって移動する。南海とは天の池である」
ほとんどありうべからざることである。しかし、ありえないと思うのは、諸君が自分らの耳や目に頼っているからであって、諸君の耳や目ははたしてそれほど信頼にたるものであろうか。
「齋諧という者がいる。彼は怪物を知っているが、そのいうところによると、この鵬が南海へ移動するとき、その羽ばたきによって海は三千里にわたって波立ち、また風は九万里の高きに及び、六月に至ってようやくやむとのことである」
「かげろうや塵挨は生き物の呼吸するものであるが、天空を九万里も昇れば、なにが見えるだろうか。地上から見上げる空はかぎりなく青いが、空の色はもともと青いのであろうか。それとも果てしなく、尽きるところがないのであろうか。また九万里の上空から見れば、この地上もまた同じように青々と見えるのではあるまいか」
「水が浅ければ、大きな舟を浮かべることができない。ところが、杯の中の水をちょっとこぼしても、塵挨はたちどころに浮かびあがる。では杯も浮かぶかというと、すぐ底についてしまう。これは水が浅くて舟が大きいからである。風もまた同じで、風の量がじゅうぶんでなければ大きな翼をのせることができない。ゆえに九万里も昇れば、その下に風が集まり、その背に天をのせ、さえぎるものもなく南へ向かうことができるのである」
そんなバカなことがあるものかと笑いとばす者があるにちがいない。なぜならば、蝉や鳩のようなものは、低い樹の梢に向かってとび上がろうとしても、うまくいかないときは地に落ちることさえあるからである。「九万里だって?ご冗談を!」と彼らは笑うのである。
「ハイキングに行く者は」と荘子は言う。「一日分の弁当を持って行けばよい。百里を行く者は前の晩から米をついて食糧の用意をすればよい。だが、千里の旅をする者は、数ヶ月も前から食糧の準備をしなければならない。蝉や嶋のような虫けらどもになんでこのことがわかろう。小知は大知に及ばず、生命の短い者には生命の長い者のことがわかるはずがないのである」
「考えてもみるがいい。茸のある種のものは朝開いてまもなくしぼんでしまうから、夕方をすら知らない。蝉は夏だけの生命だから、春も秋も知らない。かかる者は生命の短い者である。ところが楚の南にいる冥霊という生き物は五百年を一春、五百年を一秋とし、また大昔に生存した大椿は八千年を一春、八千年を一秋としていた。人間のなかで最長寿といわれる彭祖はたかだか八百歳で、しかも人間中の異例とされている。われわれ凡人の生命たるやまことに傍いものではないか」
人生の儚いことは、もとより、荘子の新発見ではない。にもかかわらず、人間が自分らの能力の限界を認識しようとせず、知を絶対視し、互いに相争っているのが荘子にはバカバカしくもあり、また滑稽にも見えた。そこで、天然現象に尾鰭をつけたり翼をつけたりして擬物化して、われわれが実在と考えているものと対決させ、人間の非力や知の限界を認識させようとしたのである。 |