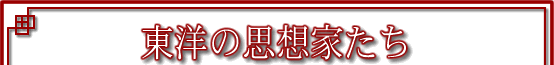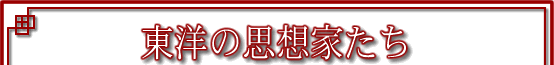南郭子綦(なんかくしき)はあくせくしたこの世の中で悠々自適の生活を送っている数少ない人間の一人である。ある日、机にもたれかかったまま天を仰いで大きな息をついていた。女房にでも先立たれたようなその茫然たるありさまを見て、弟子の顔成子游が言った。
「お師匠さま、いったいどうなさったのですか。体はまるで枯木のようで、心はまるで灰のようじゃありませんか。以前はこんなじゃありませんでしたよ」
「なかなかいい質問だ」と子綦はうなずいた。「わしはいま、自分を忘れていたところだ。おまえにはそれがわかるか。おまえは人籟(じんらい)というものを聞いたことがあるかもしれないが、地籟というものを聞いたことはあるだろうか。地籟を聞いたことがあるとしても、まだ天籟というものを聞いたことはあるまい」
「それはどういうことでしょうか?」と子游が聞いた。
「人が声を出して歌ったり、笛を吹いたりするように、大地もまた音を出すものだ。風はいわば大地のアクビのごときもので、ふだんは静かにしているが、ひとたびアクビをすれば、地上の穴という穴がことごとく鳴りはじめる。ひゅうひゅうと鳴るあの音を聞いたことがあるだろう。山林は揺れ動き、大木の穴という穴はゴーゴーと相応ずる。小風は小和し、大風は大和して鳴り響くが、風がやむと、もとのうつろな静寂に戻っていく」
「じゃ風のことですね。それなら私にもわかりますが、天籟とはどんなものでしょうか?」
「風が吹くと、大小さまざまの穴がそれぞれ音をたてるだろう。そこで音は穴から出てくるものだとそれぞれに考える。しかし、穴そのものに音があるわけないだろう。穴をして音をたたしめるもの――それがほかならぬ天籟なのだ」
人間の知識や言説にもいろいろと区別があって、大知や大言はいわば天籟のようなもので、小知や小言はいわば人籟、地籟のようなものである。大知はゆうゆうたるものであるが、小知はこせこせしたものであり、大言は火の燃えるようなものであるが、小言はペチャクチャと騒がしいものである。人間は眠りにつくと、夢にうなされるし、夢から覚めると、知覚があって接触する事物にわずらわされる。かくて日夜これ闘争となり、闘争に恐怖はつきものだから、他に勝たんものと必死になる。その結果は秋や冬が近づくように日増しに気力衰え、ついに押しつぶされたように死へと近づいていくのである。
喜びも怒りも悲しみも楽しみも、思慮も詠嘆も気まぐれも妄執も、また心配も安逸も率直も気取りも、ちょうど、穴から音が出てくるように、また地から茸が生ずるように、人間の体のなかから出てくる。これらの感情が日夜、入れ替わり立ち替わりわれわれを支配するが、いったいどうしてそうなるのか誰にもわからない。感情がなければ、我はなく、我がなければ、感情はありえない。こういう現象を見ると、たぶん、その両者をしてかくあらしむる真の支配者――かりに造物主と呼んでもよい――がいると思えないこともないが、それを確認することは不可能である。このことは肉体についてもいえることであって、肉体のあらゆる部分のなかでとくに重要な部分があるのであろうか。それともみな等しく重要なのであろうか。ある一つの部分が他をすべて支配しているのだろうか。あるいは代わる代わるに支配し合っているのだろうか。ここにも肉体のあらゆる部分をしてそれぞれの機能を果たさせる真の支配者がいるように思われるが、その存在を確認できない。できないけれども、真の支配者のあることに変わりはないのである。 |