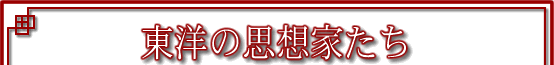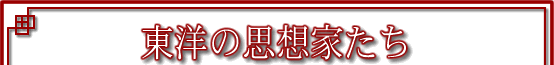|
孔子は「私は生をすら知らないのに、どうして死を知ることができよう」と言って、死について語ろうとしなかった。けれども、生と死は人間につきまとう最も重大な間題であって、哲学はこれを避けてとおるわけにはいかない。と同時に、哲学がこの問題を解決するだけの能力をもっていないことも事実である。
さしあたり疑問は、人間は死んだらどうなるだろうかということである。しかし、一度死んだ人間がふたたび生き返ることはないから、死後のことについて知ることはできない。
わずかに想像をたくましゅうして、知らないことについて知ったかぶりをするだけのことである。ところが、人間の想像がそれ自体いかにとらわれたものであるか――。
「麗姫という女は、むかし、艾(がい)というところの関守の娘であった。晉の王様が彼女を宮廷に連れて来られたとき、父親のもとを離れることを嘆き悲しんだ。ところが、御殿に連れて来られて、王といっしょの寝床に入り、山海の珍味を食べて暮らすようになってから、こんなに楽しい生活ができるとも知らないで、ワーワー泣くなんて、あのころの私はなんてバカだったのでしょうと言って王と笑い合った」(齊物論第二)
生と死の問題だって、案外、こんなものかもしれない。死ぬときは嘆くが、あとがどうなるのかわからないのだから、死後になってから、かつて嘆き悲しんだことを後悔することだってありうるのである。
夢のなかで歓楽の限りを尽くしたものは、朝になれば、現実に戻って、その厳しさに泣く。泣きつつも、朝には仕事に出かけて行く。夢を見ていたときは、それが夢であったことを知らず、覚めてはじめてその夢であったことを悟るのである。あれが夢なら、これも夢だと悟りそうなものであるが、バカはあれは夢でこちらのほうは現実だときめてかかる。
しかし、実際はいまだって夢を見ているのであって、おまえは夢を見ているぞと言っている私もまた夢を見ているのである。
これは実に不可思議不可解なことであるが、この夢を釈(と)きうる人間は、将来といえども現われることはありえないであろう。
かように、知には果てしがなく、人間の生涯は有限である。有限なるものをもって無限なるものを追えば、危険なだけで得ることはひとつもない。だから、善を行なっても名誉を求めず、悪を行なっても刑罰にふれないほうがよい。ほどよいところにとどまるのがいちばん安全で、そうすれば、生涯を無事にすごすことができるであろう。
では、生を養う道とはどういうものであろうか。
「庖丁(料理を司る丁という男)が、あるとき、梁の文恵君のために牛の屠殺をやったことがあった。手の触れるところ、肩のよるところ、足の踏まえるところ、膝のかがまるところ、まことに堂に入っていて、刀を入れると、グサリグサリと肉が切れ落ちていく。
そばで見ていた文恵君はすっかり感心して、"うまい、うまい、たいした技術だ"と賞めた。庖丁は刀を置くと文恵君に向かって言った。
"いま、たいした技術だとお賞めにあずかりましたが、私の願いは道というものでございます。私がはじめて牛を切りだしたころは、どこを見ても牛でない部分はありませんでした。ところが三年たつと、もう牛であるという気がしなくなりました。今日では目をもって見るよりは、本能的にこれを扱っています。五官の作用に頼らなくなってからは、刀が自然に肉と骨のあいだにわって入るようになり、骨や筋に当たらなくなったのでございます。ごぞんじのように腕のよい職人でも一年に一本は牛刀を取り替えます。ふつうの職人なら月に一本は替えるでしょう。私はこの十九年のあいだに何千頭の牛を扱ってきたかわかりませんが、ごらんのとおり、この刀はまるでおろしたてのような切れ味でございます。
と申しますのは、刀の刃が骨や肉のすきまにまちがいなく入っていくので、なにもないところになにもないものが入っていくように、じゅうぶんのゆとりがあるからでこざいます。
もっとも私のようなものでも、骨や筋のむらがったむずかしいところにくると、相当慎重になり、じっと見つめながら仕事をするので、行動もそれだけ鈍くなり、刀が動いているのか動いていないのかわからないくらいです。それがうまく切れて、肉がドサッと落ちるのを聞いてから立ち上がったときは、さすがにホッとしますが、それでもよくあたりを見まわして自分の意にかなったことをたしかめてから、刀をおさめるのでございます"
"なるほどね、おかげで養生の道を知ることができた"と文恵君は、あらためて感心したのである」(養生主第三)
|