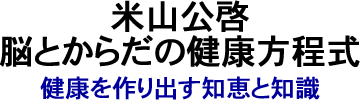|
第105回
抗生物質が効かない細菌感染
いま抗生物質が効かない細菌感染が問題になっています。
しかし、これは今に始まったことではなく、
抗生物質が使われるようになってから、
ずっと続いていることなのです。
以前はどんな細菌にでも効く抗生物質、
医学用語でいえば、
ブロード・スペクトラムを持つ抗生物質が
強力なものと考えられていました。
製薬会社もそれを売りに、医者に宣伝していました。
その結果、抗生物質を簡単に大量に使うようになって、
細菌が抗生物質に耐性を持つようになってしまったのです。
細菌も生物ですから、
自分たちがどう生き残っていくのか、
遺伝子の組み換えによって
生き残るすべを手に入れていくわけです。
これは細菌の進化の過程と考えれば当然の結果とも言えます。
もうひとつ大きな問題が実は隠れています。
それは製薬会社が
新しい抗生物質を開発しなくなってしまったのです。
以前は、抗生物質がドル箱でもあったので、
新薬開発の中心が抗生物質だったのです。
ところが、いまは高脂血症、
糖尿病など慢性疾患の治療薬の新薬開発が中心になってしまい、
新しい抗生物質が作られない
という事態になったことも影響しているのです。
抗生物質が効かないと言っても、健康な人であれば、
自分の持っている免疫力で
細菌の繁殖を抑えることができるので、
それほど恐れることではありません。
抗生物質が効かないというと、
どんな人でも感染が起きて
広がってしまうような誤解を生みますが、
ガン治療を行って免疫力が低下している人や、
高齢者が危険なのです。
院内感染ということを考えるなら、
きちんと感染症対策をしている病院かどうかを、
チェックする必要があります。
メディアで騒がれている医学情報は、
冷静に判断すべきことが多く、
それをしっかり情報発信しているメディアが
少ないのも問題なのです。 |