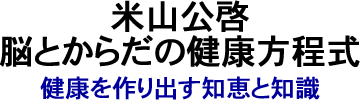|
第113回
ノーベル賞と脳
今年のノーベル化学賞を
日本人ではパデュー大学特別教授の根岸英一さんと、
北海道大名誉教授の鈴木章さんが受賞しました。
鈴木章さんの開発した炭素同士を効率よくつなげる合成方法は、
降圧剤バルサルタン(商品名・ディオバン)を製造するのに
役だっています。
ディオバンは副作用も少なく
長期的に使える薬としてよく使われています。
日本人の発想が臨床医学に役だっていると思うと
うれしい限りです。
ノーベル賞が話題になる時期にいつも思うのは、
人間というは、
生涯をかけてひとつのことしか残せないのではないか
ということです。
確かに生涯2度ノーベル賞を受賞した
ライナス・ポーリング(1954年に化学賞、1962年に平和賞)
なども例外的にいますが、
多くが一度の受賞です。
それも若いときに画期的な発見をして、
それが世間に認められるには20年、30年かかるのです。
発ガン性のあるウイルスを発見したペイトン・ラウスの研究は、
発見してから55年後に受賞しています。
少なくとも個人で
3度ノーベル賞を受賞した人はいないのですから、
いくら天才といっても脳には限界がある
ということでしょう。
しかし、そういった知性が分散しているからこそ、
いろいろな分野での発見が可能となるのです。
私たちも自分の好きなこと、
興味あることを徹底的に追求すべきです。
他の人には負けない知識や経験を積んでいくことで、
自分の脳は他の人にはない
何かを作り出すことが可能になるのです。
すべてをやることはできませんが、
ひとつのことなら可能なのです。
ノーベル賞を受賞した人たちは
徹底的にひとつのことに生涯をかけて打ち込んだ結果です。
それを見ていると、発見の大きさは違いますが、
私たちの脳の可能性を信じたくなります。
徹底的に何かをする、
そこから別の世界が始まっていくはずです。 |