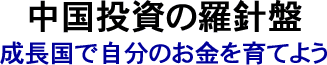|
第112回
機関投資家は市場に勝てない
販売が主で、運用は二の次なのが日本のファンドです。
「ならば外資系証券が運用するものはどうか」
という声も聞こえてきそうですが、
こちらは手数料が高すぎることが難点です。
ファンドを設定する会社は、
日本国内の証券会社などを通じて販売するわけですから、
手数料が二重に取られる分、
どうしてもコストが割高になってしまうのです。
ファンドの場合、購入する際に
1.0−3.0%程度の申し込み手数料(販売手数料)を取られるうえ、
毎年1.2−3.0%の信託報酬や管理運用報酬を取られるものが多い。
なかには売却して現金化するときに
さらに手数料を取るものもあります。
最近は購入時の手数料がいらない
「ノーロード型投信」も登場してきていますが、
それでも毎年の手数料は取られますので、
少なくともこれ以上の収益が出ていないかぎり、
投資家は損をしてしまいます。
仮に販売手数料3%という中国株ファンドを10万円購入しても、
最初に3000円がまず差っぴかれる計算になります。
反対に自身で現地の証券会社に口座を開設し、
インターネットで取引した場合、
そのコストは香港株の場合、約0.25%。10万円なら250円です。
たかが2750円の差ぐらい、と考える方もいるでしょうが、
塵も積もれば山となるで、投資資金が大きいほど、
株価の値上がりが激しいほど、
こうしたわずかな差がリターンの大小に如実に表れてきます。
ファンドを運用するプロ(機関投資家)の大多数が
市場より良い成果を上げられる、
という基本的な前提は正しくありません。
なぜなら、莫大な資金を有する機関投資家のそのものが
市場で、自身の動向がマーケットの動きを左右するからです。
いかなるプロでも自分自身に勝つことはできないのです。
そして、こうしたファンドのなによりの欠点は、
その保有する運用資金が膨大なため、
投資対象もおのずと時価総額の大きい銘柄に限られ、
成長・中国を代表するような、
小粒でも大躍進が期待できる銘柄を取りこぼしてしまうことです。
2000社以上の企業が上場している東証と違い、
日本の個人が投資できる中国企業の数は、
香港市場に限っていえばいまのところ600社未満。
インターネットの発達や関連書籍の増加などにより、
中国株の情報は以前より格段に入手しやすくなりましたから、
各銘柄の内容を丹念に調べていくのもそれほど苦労しないはずです。
|