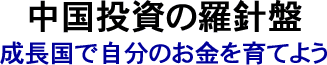| 第183回
内陸部を中心に百貨店の売上げは右肩上がりをキープ
セクター分析、第3回目となる今回は
日本人投資家の人気も高い、
「小売セクター」にふたたび脚光を当ててみました。
経済成長にともなう可処分所得の向上などを受け、
拡大を続ける中国の小売市場。
他の業界などに比べて、関連企業の業績は堅調とされますが、
百貨店、スーパー、家電など、扱う商品によって
売上高総利益率などが異なるため、
実際の収益の伸びには大きなバラツキがでそうです。
2011年1−11月の社会消費財小売総額は
前年同期比17.3%増の1兆6129億元で、
食品・たばこ、アパレル、ジュエリー、家電・ステレオの
売上高伸び率は、それぞれ24.7%、22.5%、16.2%、25.0%
となっています。
旧正月休暇の効果などもあり、
今年初めの消費財の小売総額は堅調な伸びをキープ。
GDPなど経済成長の鈍化を受けて、
今後、その販売額の伸び率に
歯止めが掛かるとの観測もありますが
インフレの一服などから、
トータルの伸び率は例年並みを維持しそうです。
以下、業種別の見通しを簡単にまとめてみました。
■百貨店:
この業界の特徴は産業集中度が低いということで、
売上ベースでトップ10の企業のトータルシェアは13.3%しかないため、
今後は大手による業界再編が進むと予想されます。
現在、個人消費が中国のGDPに占める割合は
35%前後まで増加していますが、
百貨店の総売上高はアメリカの6分の1程度にとどまっているため、
今後のキャパシティーは膨大です。
都市化や工業化の加速も個人消費を押し上げる要因の一1つ。
内陸部を中心に百貨店や小売業の売上げは
右肩上がりをキープしそうです。
インフレ期における企業収益の動向は
そのコスト転嫁力によって左右されますが、
百貨店の多くは売上歩合制を採り、
売上高のおよそ20−30%をテナント料として徴収、
また最低保証額も設けられているため、
百貨店側の収入は比較的安定。
インフレに強い業種の1つといえいるでしょう。
一般的には知名度の高い百貨店は消費者の人気も高いことから、
優秀なブランドを集めることができ、
売上も大きくなる傾向があります。
この業界では浙江省を基盤にデパートを経営している
『銀泰百貨』(01833)などに注目。
同社は最近、江西省ウイグル自治区の柳州新銀投資評価プロジェクトと、
陝西省西安の西安城プロジェクトに出資したほか、
安徽、北京、陝西、湖北、内モンゴルなどにも出店計画を持っており、
2011−14年にかけて順次開業する見込みです。
■スーパー:
この業界の企業集中度は百貨店とは反対に高く、
トップ10企業の合計シェアは60%以上に達しています。
今後の収益のカギは人件費などコストの増減です。
この業界はもともと競争が激しく、
扱う商品のほとんども生活必需品で、粗利益率が低いため、
コストの増減が即、収益の増減に結び付きます。
このところ政府主導で行われているベース賃金のアップや
テナント料の上昇は、関連企業にとって頭の痛い問題です。
(次回につづく)
|