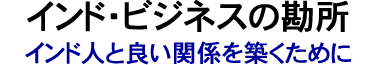|
第33回
カースト制について(その1)
今回からは3回にわたり、カースト制度について書いてみます。
カースト制度は、紀元前1000年頃、
それ以前にインド北西部のカスピ海周辺地域から
インドに侵入してきたアーリア人が、
先住民を支配した際に作られたものです。
アーリア人は先住民を支配するために神話を作り、
それを基にバラモン教を作り、そしてこれを正当化、
制度化していったものとされています。
カーストは基本的にバラモン、
クシャトリア、ヴァイシャ、シュードラの4つに分けられ、
その中でさらに細かく分類されています。
加えてこの4つのカーストのさらに下に「不可触民」、
「ダリット」とも言われ、
もともとはカーストの中にも入ってなかった
「指定カースト」の人々もいます。
農村部では、上位カーストと同じ井戸を利用したり、
ともに食事をしたりすることが許されず、
同じ寺院に参拝することも許されていません。
ダリットはインド全国民の2割弱、
後進カーストのシュードラは5割弱いると言われています。
カーストは親から子へと受け継がれ、
結婚も基本的に同じカースト内で行われます。
現在インド社会では、
カーストの影響は徐々に小さくなってきていますが、
異なるカースト間での結婚は、今でも困難です。
地方では異なるカースト間で結婚しようとする娘を
親が殺すという事件も起きています。
カースト間の移動は、認められていません。
ただ現在の人生の結果により、
次の生で高いカーストに上がることができるとされています。
現在のカーストは過去の生の結果であり、
それを受け入れて生きるべきとされ、
カーストはヒンドゥー教の根本的な世界観である
輪廻転生と結びついた社会原理です。
カースト制は世襲的に細分化された
職業に結び付けられており、
各階層の人々はそれぞれの階層にとどまるようにされています。
例えばダリットの多くは、
ゴミ回収や清掃、食肉処理業などへ従事するものとされており、
その多くは貧困状態におかれたままとなっています。
|