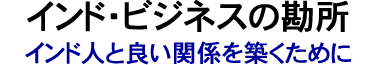|
第34回
カースト制について(その2)
今回は、カースト制度の2回目です。
現在インド政府は、貧困の解消を最優先課題としています。
またシュードラやダリットあわせて、
人口の半数以上が被差別カーストであり、
大票田として彼らへの優遇策を次々と打ち出しています。
政府は公共事業関連の仕事や議会の議席、
大学の入学枠など
下層カーストのための一定の枠を確保しています。
例えば下層カースト出身の学生に対する公務員、
国営企業職員の優先就職枠は、
1950年では20%だったものが、
93年には49.5%にまで引き上げられています。
一方優遇の対象外の人は、これは逆差別だと反対しています。
ただ新しい産業で、カーストによる
就職制限の規定がないIT業界には、
このような優先就職枠も、
下層カーストに対する就職差別も全くありません。
インドのIT業界が完全に実力主義を貫けたことは、
インドのIT業界を発展させた要因のひとつと言われています。
さらに、指定カースト出身の政治家、
役人、判事なども増えてきています。
1997年にはインドではじめて
指定カースト出身のナラヤナン大統領が誕生しています。
また06年に最高裁長官になった、
K.G.バラクリシュナン氏もそうでした。
インド北部の、
インドで最も人口が多いウッタルプラディシュ州では、
ダリット出身の女性マヤワティ氏が率いる大衆社会党が
同州で21%いる最下層のダリットを中心に支持を集め
政権を取り、彼女は州首相となっています。
現在インドでは、1950年の新憲法で
カースト制に基づく差別は撤廃されていますが、
カースト制そのものの廃止は明文化されていません。
ただしカースト制度は、今日目に見えて弱まってきています。
特にカースト毎のコミュニティーが存在しない都市部では
カーストの影響はほとんどなく、
自分の属するカーストを知らない人すらいます。
ただ農村部では、
カーストに基づく生活規範や差別が今でも根強く残っています。
|