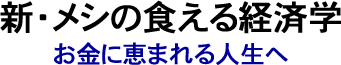|
第8回
お金は形があるようで形がなく、形がないようで形がある
お金というものは、見る人によって違った姿をしている。
形があるようで形がなく、形がないようで、形がある。
私はお金のことを考えるたびに、「荘子」に出てくる
「混沌、七窮に死す」という話を思い出す。
ご承知のように、「荘子」のこの寓話は、
人間の作為や分別が自然の動きを窒息させる愚かさを
諷刺したものと解説されているが、
私には渾沌すなわち金銭という気がしてならない。
「荘子」の一番最後の応帝王篇のそのまた最後のところに、
次のような文章が出てくる。
「南海の帝をシュクと為び、北海の帝を忽と為び、
中央の帝を渾沌と為ぶ。シュクと忽と、ある時、
相与に渾沌の地に遇りあえり。
渾沌のこれをもてなすこと甚だ善し。
ショクと忽と、渾沌の徳みに報いんことを謀りて日わく。
”人は皆七つのあなありてもって視、聴き、食らい、息するに、
此れ独り有ることなし。嘗試に之をうがたん”と。
日ごとにーつのあなをうがちしが、七日にして渾沌死せり」
シュクと忽は、シュク忽という言葉があるように、
「束の間」というホンの短い時間のことである。
束の間の生命を象徴する南の海の支配者と北の海の支配者が、
あるとき、その真ん中にある
渾沌という支配者のところでおちあった。
渾沌は二人を盛大に歓待したので、二人はすっかり喜んで、
何とかその徳に報いようと考えて、
「人間は皆、目耳口鼻の七つの穴を持っていて、物を見たり、
音を聞いたり、美味を食べたり、息をすることができる。
だのに揮沌にはどこに何があるのか、さっぱりわからない。
そこで、二人で相談して、
渾沌にも人間と同じような顔形をつくってやろう」と思い立ち、
毎日、一つずつ穴を彫ってあげたところ、
穴が全部できたところで、
渾沌は死んでしまったーというのである。
「混沌」といえば、物事の区別がつかず、
何が何だかわからない状態をさすが、
お金はまさにそういったものではないかと思う。
お金があれば、欲しいものは何でも手に入るし、
おいしいものは何でも食べられる。
人の心をひきつけることもできるし、
人を殺すことすらできる。
だから、お金にめぐりあえば喜ぶし、
その値打ちもわかっているだけに、お金
を大切にする。
しかし、お金はきまった形を持っておらず、
時に土地建物に化けるかと思えば、
時には黄金や宝石に変身してしまう。
かと思えば、次の瞬間には、船に形を変えたり、
飛行機に乗ってどこか地球の果てまで姿を消してしまう。
そういう融通無碍な存在を、
何とか思いのままにできないものか、
と人々は昔から考えてきた。
とりわけ権力を振るった為政者たちはそのことに熱心であった。
戦争中の統制経済とか、マルクスの唱えた私有財産の否定とか、
外国為替の人為的な統制とか、
資本主義たると、共産主義たるとを問わず、
人民に言うことを聞かせられる立場の人たちは、
必ずのようにお金も自分たちの意のままに動かそう
という執念にとりつかれる。
それを「荘子」は、七つの穴、つまり、
「人間の形」にたとえたのであろうが、
人間にとって扱いやすい形になおそうとした途端に、
お金は死骸だけを残して、
いずこへともなく消え去ってしまうのである。
資本主義におけるお金のコントロールの仕方は、
まだせいぜい税金とか為替制限とかくらいなものであるから、
お金はまだ隠れ家や避難所を求めて逃げ隠れすることができる。
ところが、共産主義のように、
穴という穴を封じ、有無をいわさず抑え込んで
手錠をはめるようなやり方をすると、
お金そのものが息絶えてしまう。
共産主義の支配する国がどこも、
お金と縁遠くなってしまったのは、
無理矢理、お金に言うことを聞かせようとしたからである。
お金の性質を考える限り、
こうした強硬手段はあまり効果がない。
腕力や暴力に物をいわせてお金を手に入れることができても、
向こうにその気がなければ、
長くは手元にとどまっていてはくれないからである。
何しろお金はどんな形にも化けるし、
どんなものとも入れ替わることができるし、
手足をしばっても、目隠しをしても、
戸の隙間からでも鍵穴からでも、
スーッと音もなく消え去ってしまう超能力の保持者なのである。
したがって、お金とつきあおうと思えば、
渾沌とつきあうのと同じく、
まずその性質を熟知していなければならない。
|