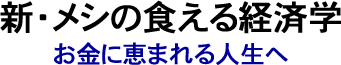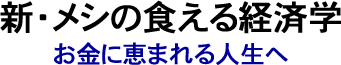|
第13回
人と人を結びつけるものはお金である
人と人をつなぐ最も強力な接着剤は、
「残念ながら」お金であろう。
お金を卑しむ気持ちの強い人から見ると、
「残念ながら」と言うよりほかないが、
それは本当のことである。
私はお金儲けのセンセイということになっているが、
お金が万能と思っているわけでもないし、
お金以外の他のものが重要でないと思っているわけでもない。
しかし、お金にどんな力があり、
人間の心理にどんな影を落すかは知っているつもりである。
人と人とをつなぐものはお金である。
共通の利益関係といってもよい。
メシの種と言いなおしてもよい。
戦前の日本の教育勅語は、
「君に忠に、親に孝に」と教えたが、
君恩に報いるに忠誠をもってしなければならないのは
メシを食わせてもらっているからであり、
親孝行をするのは、利害を度外視して育ててくれた親の愛に
感謝の気持ちを持っているからである。
「君に忠に」という場合の「君」は
国の元首という意味になるが、
徳川時代の「君」は各藩の藩主であった。
どうして藩主に対して忠誠を誓わなければならないかというと、
当時の経済単位は藩になっていて、
藩主あっての藩士であり、
忠臣蔵の中の赤穂浪士を見てもわかるように、
お家取潰しが決定すると、
藩士たちは失業の憂き目にあったのである。
だから、家来が殿様に忠実に仕えるのは、
殿様に忠実というよりは、自分の米櫃をしっかり守る
ということにほかならず、
純粋に精神的なものであると考えるのは、
いささか現実を無視した物の見方ではないかと思う。
もちろん、物質的なつながりは
やがて物質以上のつながりをつくり出す。
管鮑の交わりとか、刎頸の交わりとか、
利害を超えた友情の厚さを示す故事がいくらも残っているように、
この世に生きて生死を共にする気を起こさせる友人に
めぐりあえたら、こんなしあわせなことはない。
しかし、真の友情だけでこの世はつくられているわけではないし、
二人や三人の友人だけで世の中が渡れるものでもない。
世の中は、仕事を遂行したり、お金を稼いだり、
家族を養っていかなければならないので、
そのために役立つ人に目をかけてもらったり、
一緒になって駕寵を担いだり、
うまく利用させてもらったりする必要がある。
人と人との関係をうまくやっていこうと考えるのも、
そうしなければ、淋しい人生になるから、というよりは、
その方が人生のプラスになるから、
という積極的な意味にとった方がいいであろう。
|