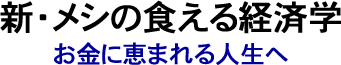|
第63回
財産三分法も国際化の時代に入ってきた
不動産の価格も色槌せ、
株価も十何年前の水準まで押し戻されてしまった。
こうなると、土地への一極集中は全くの時代遅れで、
財産三分法が再び息を吹きかえしてくる。
実は、昭和三十九年の大不況の頃も、
昭和四十九年の石油ショックのときも、
また今次のバブルのはじけたあとも、
産業界が不景気で苦しむときは、
いつも株価や地価が暴落して
現金の値打ちが大きくクローズ・アップされている。
そういうときは財産三分法が改めて説得力を持つようになる。
つまり、財産三分法が説得力を持つということは、
いい世の中ではないという証拠みたいなものである。
もし今後も大不況が定着し、
それが長期化するとすれば、みんな昔ながらの生活に戻って、
財産三分法をもう一度よく噛みしめる必要があろう。
しかし、いま日本にきている大きな変化は、
たぶん、昭和の初め頃に戻って
みんなで失業の苦しみを味わうことではないだろう。
新しい変化は人々の行動半径を広げ、
グローバルな活動を可能にするものであるから、
財産三分法もグローバルな視野で
考えざるを得ないところまできてしまった。
いま、証券会社が外債を投資家にすすめたり、
銀行を通じて外貨預金をする人が増えているが、
同じ現金預金をしたり、債券を買ったりするのも、
日本の国債や日本円とは限らなくなっているのである。
ほんの少し前までは、定期預金といえば円建てで一年とか、
半年とか、期限を切ってお金を銀行に預けておくことであった。
ところが、空前の低金利になって円建てでは
〇・五パーセントしか金利がないようになると、
その十倍も、十五倍も金利をくれる外貨はいくらでもあるから、
そちらへ横滑りしようかという動きが出てくる。
一般に金利の高い通貨は国際的に基盤の弱い通貨というのが
常識だが、米ドルと日本円、
あるいは、米ドルとマルクの関係を見てもわかるように、
いままでがそうだったから
今後もそうだと断言のできない未知数のところがたくさんある。
そうなると、財産三分法だって、
円建てで発想するだけでなく、
ドル建て、マルク建て、
更には他のさまざまな通貨の動きも考慮の中に入れざるを得ない。
神経を使う分野が広がった分だけ
悩みのタネも増えることになるが、
お金の動きが世界的に広がった以上、
守備範囲を日本というグラウンドの中に限ることはできなくなる。
財産三分法も、国際化の時代に入ってきたのである。
|