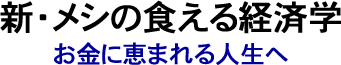|
第108回
どの町でも金持ちはよそ者
ふつうの商売では、親から子へ、
子から孫へと代々家業を受け継いでいくケースが多いが、
経営的には、よく言われるように二代目、
三代目のほうがずっとむずかしい一面がある。
ある意味で、創業者以上の才覚が要求されるのではないだろうか。
親のやり方をマネて、
漫然と同じ商売を続けているだけでは、
発展どころか現状維持さえむずかしいだろう。
たとえば、フランスあたりの料理店、
レストランというのは、ほとんどが一代限りなのである。
店の代が替われば、当然味のほうも変化するから、
以前の味にひかれて来ていたお客さんたちは
寄りつかなくなってしまう。
かといって、いかに息子といえど
親とそっくりそのままの味を出すのは困難だろう。
そのへんの事情をよく承知しているからこそ、
血のつながった子どもにも跡を継がせないのである。
これを逆にいえば、親から商売を受け継いだ子どもは、
むしろ親と違ったことをしなくてはいけないということになる。
経営方法一つとってみても、
親のやり方をそのまま踏襲するばかりでは、
いずれ時流に合わなくなる。
いまの世の中はことに動きが激しいから、
旧来のやり方オンリーではなかなか通用しないのである。
その意味で、後継者たる者は、
親から受け継いだ商売を守るというのではなく、
つねに発想の転換というか、
攻撃的な姿勢を打ち出す必要があるだろう。
近ごろは、地方都市へ行ってみても、
昔からの商売を守って立っている店は非常に少なくなった。
いま生き残っているのは、親とは別の商売を始めたとか、
経営方法をまったく新しいスタイルに切り替えていったとか、
そういう店がほとんどである。
そもそも、地方都市の商売には
つねにある一定の原則が働いているのだが、
そのーつは、地元で商売をやって
大金持ちになる人間は少ないということである。
金持ちは、みんなよそ者である。
ちょうどホステスや風俗嬢などと同じで、
自分の生まれ故郷でガツガツ金を稼ごうとはだれも思わない。
というのも、商売には"恥をしのんで"という面もあるし、
また競争関係に立って、
お互いに気まずくなる面もあるからである。
私の経験でも、土地の成功者に会って
「この町のご出身ですか」とたずねると、
たいてい「いいえ」という返事がかえってくる。
この成功者が次の子どもの代になると、
今度はまたよそから一攫千金の志を持った
ライバルが入ってくるので、
土地の人間である二代目は非常に商売がしづらくなる。
結局、親の代からの商売を捨てて、
新しいことを始めた人がかろうじて残っているのである。
|