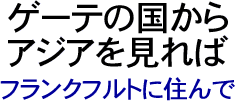
伏見緑さんが語る「あなたの知らないドイツ」
|
第71回 硬水のドイツの水を甘く見て、 加えて、内陸ゆえのこの乾燥状態、 一晩たてば、水道の蛇口やシンクなど水分がとんで、 限りなく純水に近いとも言えそうなほど軟水国、 水を使えば使うほど厄介ごとが増えるので、 「水」に関した日本のことわざを |
| ←前回記事へ |
2007年4月18日(水) |
次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |
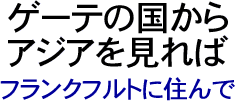
伏見緑さんが語る「あなたの知らないドイツ」
|
第71回 硬水のドイツの水を甘く見て、 加えて、内陸ゆえのこの乾燥状態、 一晩たてば、水道の蛇口やシンクなど水分がとんで、 限りなく純水に近いとも言えそうなほど軟水国、 水を使えば使うほど厄介ごとが増えるので、 「水」に関した日本のことわざを |
| ←前回記事へ |
2007年4月18日(水) |
次回記事へ→ |
| 過去記事へ | ホーム |
最新記事へ |