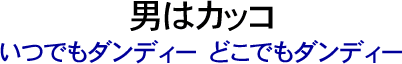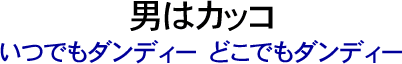|
第828回
ある一冊の本から考えること
生地屋をのぞいてみることがありますか。
私は生地屋へ行くのが大好きです。
何を買おうというのではない、
何を仕立てようというのではない。
まさにジャスト・ルッキングのことが多い。
パン屋にパン屋共通の匂いがあるように、
生地屋には生地屋の匂いがある。
店に入ったとたん漂ってくるあの匂いに、
懐かしさを感じるのです。
なにか心が落着かないような時、
生地屋へ入ってひとまわりすると、
私はすっかりいつもの自分を
取りもどすことがあります。
今、ここに一冊の本があります。
題して『フランスの布』。
副題に“アンティーク・プリント 1946-1959”と書いてある。
今からざっと半世紀前の、
プリント生地ばかり集めた本なのです。
(文化出版局刊 1,800円)
「フランスの布」というと、
すぐにオートクチュールの世界を想像して、
豪奢の極緻かと思いますが、
そうではありません。
基布はたいていコットンやリネンです。
プリント地の生地のことを基布(きふ)と言います。
プリント柄の多くは童画の世界そのもので、
しかもごくごく素朴なものです。
少女のサマー・ドレスを仕立てるのに
最適であったろうと思われます。
柄自体もナイーブなら、
配色もまたナイーブで、
下手なビタミン剤よりも、
はるかに元気を取りもどす効果がありそうです。
つまり生地屋を2、3軒はしごしたくらいの
効力はあるのではないでしょうか。
第二次大戦直後のフランスでは、
母が子に服を仕立ててやるのは、
さほど珍しいことではなかったのでしょう。
この事情はなにもフランスだけのことでなく、
もちろん日本でも似たようなことがありました。
今、私は生地と型紙を買って、
子供に服を作ることは絶えてありません。
でも、かつてそんな時代があったことは忘れたくない。
服だけに必ず、なんでも買えば良いのではない。
下手でも不器用でも、
自分で作れるなら作るべきです。
感情がこめられていないものより、
心あるもののほうが、
はるかにおしゃれなことなのですから。
|