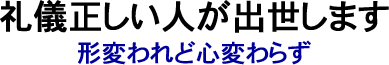| 第31回
小正月
皆さんは『小正月』という言葉をご存知ですか?
旧暦を使っていたころは、
一年の最初の満月にあたる1月15日を「正月」としていました。
(今年は1月11日が満月でした。)
太陽暦を用いるようになって、元旦を正月とし、
1日を大正月、15日を小正月と呼ぶようになりました。
小正月には『どんど焼き』を行います。
これは、正月飾りや書き初めなどを焼く行事で、
飾りに憑いた年神様をお送りし、
無病息災を祈る火祭り行事。
この火で餅などを焼いていただく地域もあります。
残り火で焼いた団子をいただくと、
病気をしないといわれています。
たき火の炎から放射される遠赤外線は、体を芯から温め、
血行を良くし、代謝を促進します。
また、体内の不要物を排出する効果もあり。
また、煙や炭は抗菌・雑菌作用や抗酸化作用があるので、
煙を浴びることも体に良い。
ただし、浴びすぎるとむせるので要注意。
そして、小正月には『小豆がゆ』をたべて、
健康を願うならわしがあります。
小豆の赤は魔除けの意味を持つところから、
一年の無病息災と厄払いの意味を込めています。
新年明けて2週間。
一旦の休息とこれからの一年間に向けて、
再度、心も身体も小豆がゆで温めてみてはいかがでしょうか?
<小豆がゆレシピ♪>
材料 小豆 水 米 塩 餅
1. 小豆はよく洗って水に一晩浸けておく。
2. 小豆をつけ汁ごと鍋に入れて強火にかけて
沸騰したら弱火にして柔らかく煮る。
3. 米はといでザルにあげておく。
4. 小豆が柔らかく煮えてきたら米を加えて火を強める。
5. 沸騰したら弱火にして30分炊く。
6. 火をとめて塩で調味。
7. 食べやすく切ってこんがり焼いたお餅をお好みで。
|