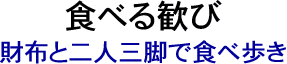| 第659回
年末に食べちまったおせち料理(その2)
年が明ける前の12月30日に大胆にも
麻布十番「かどわき」のおせち料理の蓋を開いた。
 |
いくらの柚子釜を真ん中に据えた一の重
photo by J.C.Okazawa
|
ちょいと判別しにくいが
いくらには金粉で「寿」の文字が刻まれ、
なかなかに趣向をこらしているのが判る。
さっそく一の重の内容の紹介といきたい。
くだんのいくらを中心に、その下が丹波の黒豆。
以下、時計回りに、焼き帆立貝柱、穴子八幡巻き、
鴨ロース、金時人参煮、栗渋皮煮、人参と大根のなます、
数の子、茹で車海老、梅酒の梅の衣揚げ、昆布巻き。
以上、10品である。青字は特筆モノだ。
こうしてみると、おせち料理の良し悪しは
たぶんに食材の質に左右されることが判る。
もちろん黒豆を煮たりするのは
板前さんの腕に依るところが大きいのだろうが
それほど手の込んだ料理が見当たらないおせちは
良質の素材の確保が肝要なのである。
案の定、白ワインのムルソーは期待通りに
ほとんどの料理とハーモニーを奏でてくれた。
ただし、数の子だけは例外だった。
これは数の子の製造に不可欠な何かしらの
化学薬品がワインとの調和を妨げているからだ。
20年も昔に、そのときは赤ワインだったが
数の子入りのわさび漬け、
いわゆる山海漬けと合わせてみたら、
その相性が耐えられぬほどに最悪だった。
てっきり山海漬けに含まれる酒粕が
その要因と思いきや、そうではなく
数の子が赤ワインと協調しなかったのである。
鴨ロースは2本目のワイン、
オーパス・ワンに合わせた。
続いて二の重を味わうことに。
 |
珍味が満載の二の重
photo by J.C.Okazawa
|
こちらは凝りに凝っていた。
おせちの定番が目立った一の重とは様変わりだ。
内容は、前列が左から
子持ちにしん酢〆、さわら塩焼き、
平目昆布〆、揚げ湯葉、蒸しあわびと絹さや。
中列の炊き合わせは
地だこ・鞠麩・八つ頭・天豆・しいたけ・こんにゃく。
後列は左から
焼き雲丹と子うるか、黒トリュフの玉子焼き、
からすみ、サーモン餅。
個人的には二の重に軍配を挙げたい。
殊に真ん中で存在感を示す炊き合わせが白眉だ。
食材の取り合わせが秀逸で目と舌を和ませてくれる。
玉子焼きのトリュフは
おい、おい、こんなに入れてどうすんの?
そう言いたくなるほどの豪華版であった。
ワインを飲み干し、再び缶ビールに戻って
あとはひたすらカラオケにいそしむ。
気がつけば、時計は午前1時を回って
すでに大晦日に突入しておりましたとサ。 |