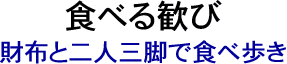| 第734回
蝦蛄と穴子と蛤と(その3)
「弁天山美家寿司」で本まぐろと
本玉(赤貝)ヒモ入りのぬたに舌鼓を打っている。
金冠大関の燗もほどよく、自然に笑みがこぼれる。
親方の直下、二番手の兄さんが
「そろそろにぎりますか?」と訊ねてきたので
「そうだね、その前にもう一品かな・・・」と応じる。
つまみの締めくくりは、さよりの糸造りであった。
ここでさよりが登場したということは
にぎりのスタメンには入っていないのだろう。
さあ、いよいよ10カンにぎりの浅茅のスタートだ。
にぎりは5カンずつ二度に渡り、
下駄を履いて供される。
まずは第一の下駄。
 |
どれから食べてやろうかな・・・
photo by J.C.Okazawa
|
当代の五代目は先代よりもやや大きめににぎる。
左下から時計回りに
黒みる貝・平目昆布〆・小肌・真鯛松皮・赤貝。
J.C.は、平目・小肌・真鯛・黒みる・赤貝の順に
いただいた。
前半のMVPは小肌だ。
努めてとんがり気味に仕上げた酢加減が
「弁天山美家古」の伝統を静かに物語る。
黒みる貝、またの名を本みる貝は
ナミガイとも呼ばれる白みる貝とは
比べ物にならぬくらい、旨みに奥行きがある。
続いてのセカンドハーフ。
 |
穴子の存在感がひときわ光る
photo by J.C.Okazawa
|
やはり左下から時計回りに
穴子・赤身づけ・玉子・車海老・煮するめいか。
これは、煮いか・穴子・づけ・玉子・車海老の順に。
沢煮をあぶり、煮ツメを一刷毛引いた穴子が白眉。
歯の生える前の乳児や歯の抜けた老人でも
難なく食べられるようなフンニャリ穴子が
横行する世の中にあって
「美家古」の穴子は孤軍奮闘。
他店にももっと見習ってほしいシゴトである。
歯ざわり快適な煮いかが穴子に続く。
刺身はやりいかだが、煮いかはするめいかだ。
このプツリプツリとした食感が何とも言えない。
よそで見掛けるやりいかの印籠詰めも好きだが
どちらがと問われれば、躊躇なく煮するめいかを選ぶ。
鞍掛けの玉子とおぼろをカマせた車海老の
ほのかな甘みを楽しんでも、まだまだ箸を置くには早い。
ここで各自、好きなものを追加注文していく。
ある者は小づけ丼に走り、またある者は
スタメンを外れていた本まぐろの中とろを所望する。
J.C.は、蝦蛄と煮蛤をリクエストした
 |
大ぶりの煮はまぐりと蝦蛄
photo by J.C.Okazawa
|
江戸前が枯渇している蝦蛄は三陸モノだろう。
「美家古」流にしっかりと煮上げられている。
蛤はこれほどのサイズなのに
歯に当たる硬い部分がまったくない。
穴子と蝦蛄と蛤と、煮ものトリオの揃い踏みに
舌の鼓をポンポンポンと打ってきた。
【本日の店舗紹介】
「弁天山美家古寿司」
東京都台東区浅草2-1-16
03-3844-0034
|