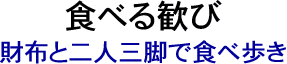|
第987回
花咲き誇る余丁町(その1)
東京都・新宿区・余丁町は大した町である。
突き詰めていえば、
ここの住人たちが大した連中なのであった。
それも四半世紀も前に棲んだ人たちが――。
ときは1986年。
昔からお上の愚行は枚挙にいとまがないが
典型ともいえるのが郵便配達の利便性だけを
追求した結果の新住居表示。
アホな役人のおかげで幾多の趣きある町名が消え去った。
余丁町も例外ではなく、本来ならそのときに
東新宿×丁目と改悪される運命だったのである。
このときに立ち上がったのが当時の住民たちだ。
甲斐あって古式ゆかしい町名が残っただけでなく、
周辺の河田町・富久町・市谷台町・住吉町などが
こぞって生き延びるさきがけとなった。
これすべて余丁町住人の功績である。
江戸時代には旗本の組屋敷があった土地ながら
明治以降は文学の匂い立ち込める町となり、
かつては坪内逍遙や永井荷風も移り住んでいる。
荷風の著名な日記文学「断腸亭日乗」の断腸亭は
余丁町の居宅の玄関脇にある六畳間のことを指す。
わが愛読書、浅田次郎の筆になる、
天切り松シリーズの主人公は村田松蔵。
その親分が目細の安吉だ。
東京地検の白井検事と全面対決する以前、
目細一家がアジトを構えていた場所が余丁町の西端、
八幡太郎義家ゆかりの厳島神社、通称・抜弁天である。
春まだ浅き日の昼めしどき。
こちらは夏目漱石ゆかりの夏目坂。
その中腹にある天ぷら店「高七」にいた。
目の前には本日の日替わり定食が運ばれている。
 |
日替わりは天ぷら定食+焼き牡蠣
photo by J.C.Okazawa
|
殻付き牡蠣のコキールは
“厚岸産オリジナル焼き牡蠣”を謳っており、
これはマヨネーズ焼きのこと。
天ぷらの内容は、海老・きす・
いか&そのゲソ・下仁田ねぎ・さつま芋・大根。
珍しい大根は抹茶塩でいただいて存外に美味。
青海苔と豆腐の味噌椀も丁寧に作られ、
これが千円ならまったく文句はない。
ここで腹ごなしに思いついたのが
余丁町散策だったのである。
夏目坂を上りきり、抜弁天を文字通り抜けて
“まねき猫ダック”ならぬ、
まねき通りなる寂れきった商店街に差し掛かった。
 |
地方都市の××銀座を思わせる
photo by J.C.Okazawa
|
チラリと見えたミモザの花に誘われて路地に入り込む。
 |
ミモザ館とでも名付けたくなるお宅
photo by J.C.Okazawa
|
さすが余丁町、昔の建物がそこかしこに残っている。
界隈では椿の花がやたらに目についた。
 |
黒澤映画「椿三十郎」が脳裏をよぎる
photo by J.C.Okazawa
|
町内に住むのは四半世紀前に頑張った方々の
お子さんに当たる人たちであろう。
古き良き町名を残そうとする粋な血筋を引いたものか
彼らには草花を愛でる心の余裕が感じられる。
およよっ!
いきなり出食わしたノスタルジックなお店に
心をわしづかみにされた。
=つづく=
【本日の店舗紹介】
「高七」
東京都新宿区若松町36-27
03-3202-4035 |