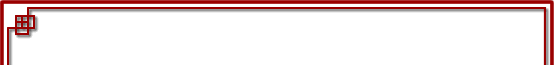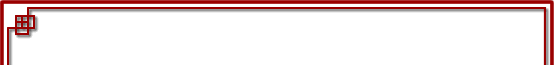衛に職を求めて与えられず、やむなく陳に行くことになった。その途次、宋の匡城を通りすぎると、突然土地の人たちに囲まれた。人々は武器を手に、口々に、
「陽貨が来た!」
と叫んでいる。これはかつて陽貨がこの土地で乱暴を働いたことがあるからであり、孔子が自分の大きらいな陽貨にまちがえられて、危く殺されそうになったのだから、似ているのは容貌だけではないという私の推測には根拠がありそうに思える。さいわいにも人違いだったことがわかり、孔子は一命をとりとめたが、そのとき彼は大きな口をきいた。
「文王は死んだけれども、文は死なず。なにを恐るることがあろうぞ」
孔子が文学青年あがりであることはあとに述べるが、年をとっても文化至上主義的な傾向が強かった。文王の精神の正しい相続人は自分であると自負している。もし自分が殺されたら、文王の精神はここで断絶してしまうであろう。そんなことはありえないから、おれは死ぬはずがない。
いささか論理の飛躍がありすぎるが、孔子が権力者に人気がなくて、弟子たちに人気があった理由は、こうした彼の教祖的な自信の強さにあったと考えられる。
孔子は宋へ行かずに衛へ帰り、衛から鄭へ、鄭からまた衛へ戻って、さらに晉に、晉から魯へ、魯から呉へ、呉から衛へ、衛から曹へ、曹から宋へ、宋から陳へ、陳から蔡へ、蔡から楚の属国葉へ、葉から蔡へ、蔡から楚へ、楚から魯の王国へと、流浪につぐ流浪の生活を続けた。
その間、彼は諸列強のあいだにはさまって実にさまざまな苦難にあい、また彼の敵や隠遁派の人々の嘲笑の的となっている。誰ひとり彼を使ってくれようとはしなかった。旅を続けているうちにしだいに顔が広くなり、どこへ行ってもぞうりを脱ぐ家ができたのがまだしもである。
「もしわしを使ってくれるものがあったら、一年だけでもよい。三年たてば、りっぱな治績をあげてみせる」
そう言ってはみるが、誰も相手にしてくれない。悲観したり、落胆したり、老子のような隠遁派になろうかと思ったりしている。
「どうしても道が行なわれないのなら、いっそ筏に乗って海に出てしまおう。そのときは、子路、おまえもいっしょに行くか」
戯れに言うと、子路はすっかり本気にした。
「おまえというやつは、なんと向う見ずの男だろうな。海へ出るにしても、筏を作る元手もないじゃないか」
仁義がすたれたことに対する慨嘆は『論語』のいたるところに出てくる。しかし、道が行なわれたことなど人類史が始まって以来、かつてなかったということもできるし、孔子が自身述べているように、多くの人が歩くから道が広くなるのであって、道が広いから多くの人が歩くのではないとみることもできる。この論理的矛盾を平気でおかす心理は、孔子の自已中心主義を念頭においてはじめて理解できるのであって、自分の不遇をかこつことばとして聞けば、いちばんよく納得できるのではあるまいか。
そんな不遇のなかにいて、孔子がつねに失わなかったものは、火よりも強い彼の自信であった。彼はほとんど口癖のように、他人が自分を知ってくれないのは気にならない、なぜ自分が人に知られないのかそれが気になるのだ、と繰り返している。裏返していえば、自分に能力があれば、必ず人に知られるに至ると考えていたのである。
あるとき、葉公(しょうこう)が子路に孔子の人物を聞いたことがある。あまり漢然とした質問で、子路はなんと答えてよいかわからなかった。ひとつには孔子という人間が、彼の最も身近にいながら、つかみどころがない男であったからにちがいない。
そのことを聞いた孔子が、子路に向かって言った。
「どうしてわしのことをこう言わなかった。憤慨すると、飯を食うのを忘れ、うれしくなると、心配事をいっさい忘れ、自分が年をとるのも知らないでいる男だと」
孔子が自分を評したことばのなかで、おそらくこの一句ぐらい、実感のこもっているものはないであろう。そして、また孔子が先入観をもたないで、もっぱら自分の直感力に頼ったことを示す好個のことばはほかにないであろう。孔子自身は「一を以て之を貫く」と言っているが、これを現代語に翻訳すれば、さしずめ「直感力」というべきであろうか。
しかし、「売らんかな」は結局、なかなか買い手に巡り会わなかった。孔子が鄭に入ったときのこと、弟子たちと道ではぐれたことがある。孔子は城の東門に立っていたが、子貢が道行く人にこれこれしかじかの人はいませんでしたかと聞くと、
「さっき東門に一人の男が立っていましたよ。頭の格好は堯帯に似、うなじは皐陶(こうよう)のようで、肩は子産にそっくりでした。しかし、腰から下は禹より三寸ぐらい低いし、それに野良犬のようにうろうろしていましたよ」
あとで子貢がそのとおり、孔子に告げると、彼は顔をほころばせて、
「前のほうの形容はあまり正しくないが、野良犬のようだとは、まったくそのとおり、そのとおり」
と言って笑いとばした。
これは『史記列伝』の記述で、作り話であることはもちろんだが、涙と笑いのあいだにあって、自分自身をも含めて笑いとばしてしまうような諧謔がなければ、おそらく孔子は彼の弟子たちにあれほど敬愛されはしなかったであろう。なぜならば、この種の「笑い」こそは、われわれの文明における清涼剤だからである。 |