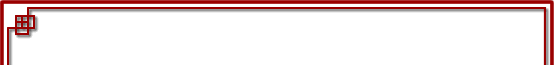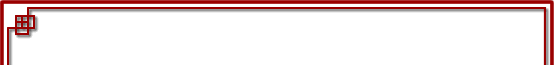不可知世界を描くことによって人間の卑小さを示すのは、東西を問わず、ロマンチシストの常套手段であるが、荘子の荘子たる面目は、そこからたちまちに神の存在へと飛躍することなく、あくまでも可知の世界へとどまろうとしたことであろう。不可知世界の支配者に支配されまいとしている点では、孔子一派の儒家と同じ側に立っているということができる。
その必然の結果として、荘子の目は大自然の方向へ向けられているように見えながら、その実、人間社会から瞬時もそれえないのである。
「その知識がその地位にふさわしく、その行いが一つの村を感化し、またその徳が一国の君主のおぼしめしにかなって国の政治に参与する者が自らを見るのも、また小鳥が自ら大となすのと似たようなものである。ひとり無抵抗主義で有名なかの宋栄子だけはニヤニヤ笑って世間の人が賞めようがけなそうが、いっこう意に介さなかった。その意味で彼は本質的なものとそうでないもの、真の栄誉とそうでないものとの区別をつけることができ、一応世俗から超然としていたが、それでもまだ完全に世外に立ったとはいえない。またかの列子は風に乗って空を飛ぶことができたが、十五日たつとまた舞い戻って来た。世を越えたという意味では、宋栄子より一枚うわてであるが、風がないと飛べないのだから、まだ完壁とはいえない。これに対して真の自由なる者は、天地の正に乗り、六気の弁を御し、空間や時間を超越した無限の世界に遊ぶ者であるから、何者をもたのむ必要がない。自我もなければ、功績もなく、名誉も問題ではないのである」
「むかし、堯は天下を許由に譲ろうとしてこう言った。"日や月が出たら、炬火をつけるだけむだなことです。雨が降れば灌漑の必要はありません。あなたが立てば天下がよく治まるものを、私がこうして政権の座にいるのは、まことによけいなことだと思います"。
それに答えて許由が言うには"あなたのもとで天下はよく治まっているのに、どうして私が出る幕がありましょう。名のためですか。名は実のお客のようなものですから、名のためだとすれば、客になれと言うわけですか。小鳥は深林のなかに巣を作っても枝が一本あればたりるし、モグラは河の水を飲んでも満腹すれば、もうそれ以上は飲めません。どうかお帰りになってください。私は天下を譲っていただいても、どうしようもないのです"」
大臣病患者がゾロゾロしている世の中を頭に浮かべながら、この文章を読めば、こういうことがありうべからざることであることはすぐわかるであろう。太古において帝位が徳のある者から徳のある者へと譲り渡されたという寓話が、仁義道徳を主張する儒家によって創作されたとするならば、「仁徳くそくらえ!」の寓話がその反対派によって創作されたとしても不思議ではないであろう。世間には名誉や利益のために生命を賭ける人間がかくも多いぞ、と言う代わりに、荘子は逆手を使って、まったく同じことを、天下には天下を譲られても迷惑だと思う人間がいますよ、と表現しているのである。こうした逆手は荘子の最も好んで採用した手法で、それを文字どおりに受け取ろうが、あるいは逆に受け取ろうが、まったく意に介しなかった。というのは、逆もまた真としてそのまま通用するのが人間の社会だからである。
「肩吾という男が連叔という男にこう聞いた。"これは接輿から聞いた話だが、どうもおおげさすぎてとても信じられんのだ。まるで銀河のようにはてしもなく、われわれの常識ではとうてい考えられない、驚くべき話なんだよ" "どんな話なんだね"と連叙がきき返した。"藐姑射(はこや)の山に神人が住んでいるというんだ。肌は氷や雪のように白く、まるで処女のように美しく、五穀を食べずに風を吸い露を飲み、雲に乗り龍を御し、どこへでも自由自在に遊びに出かけるそうだ。そして、ひとたび精神を集中させると、物を傷つけないで、しかも五穀をみのらせるというんだから、どう考えたって気違いの妄想じゃなかろうか" "さあねえ?"と連叔は言い返した。"盲は物を見ることができないし、聾は鐘や太鼓の音を聞くことができない。盲や聾というのはなにも肉体的条件だけの話じゃなくて、知識についても言えることだからね。案外、君のような人間のことをいっているのかもしれんぜ。」
「あるとき、宋の人が章甫という冠を仕入れて南のほうの越へ売りに出かけた。ところが河を渡って越へ入ると、この地方の住民は髪毛を切り体中に刺青をしているので、帽子などなんの役にもたたないのである。それを同じように、いくら天下を治めていると思ったところで、それがどこででも通用すると思うのはとんだ見当違いである。堯は藐姑射の山、汾水の北で、四人の有道者に会って、はじめて自分の卑小に気づいたのである」 |