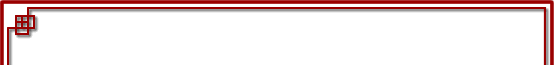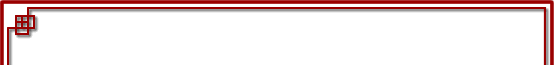|
こうした寓話は死を前にして嘆き悲しむ人間がいかに多いかを示すものであり、それを念頭において、反語的に受け取ってのみはじめて荘子の企図を理解できる性質のものである。同じように、次の寓話もまた、死を悼み、ものものしい葬式を礼とする儒教的な考えに対する反発として読むべきものであろう。
「子桑戸、孟子反、子琴張が三人は友人になろうと思ってお互いに向かって言った。
"誰か、つきあっていてもつきあっていることを意識しないでいられるような、また相手のためにしてもためにしていないような、そんなつきあいのできるものはいないだろうか。
誰か天に登ったり、霧に遊んだり、はてしない無の世界をかけめぐって、生を忘れ去ることのできるものはいないだろうか"
そこで三人はお互いに顔を見合わせて笑い合い、莫逆の友となった。
まもなく子桑戸が死んだ。孔子は早速弟子の子貢を葬式の手伝いに行かせたが、行ってみると、葬式どころか、ある者は蓆(むしろ)を編み続け、ある者は琴をかき鳴らしながら、にぎやかに歌っている。
桑戸よ、
ああ、桑戸よ、
おまえはもとへ戻ったというのに、
おれたちはまだ人間だ、
ああ、ああ……
子貢はそれを聞くと、そばへ行ってたしなめるように、
"死人を前にして歌をうたうのは礼に反しませんか"と言った。
孟子反と子琴張は互いに頭を見合わせて笑いながら、
"こいつにどうして礼の精神がわかるかい"と言った。
子貢は帰って孔子にことのしだいを報告した。"いったい、あいつらはなにものですか。不謹憤にも、死体を前にして歌なんぞうたって、まったく救いようがないですね"
"やつらは浮世の外に遊ぶ連中で、わしらとは考え方が違う。それを知っていながら、おまえを弔いに行かせたのが悪かった。やつらは造物主を自分らと同じ者とみなして、天地自然に遊ぼうとしている。生をコブかイボのように考え、死をデキモノがつぶれたぐらいに考えている。そういう連中にどうして生と死のけじめがわかろう。生と死を同じものだとみなして、肝胆も耳目も忘れて、はじめも終わりもみそくたにしているんだから世俗の礼などわかるはずがないよ"
"では、先生はどちらの肩をもちますか"と子貢が聞いた。
"わしは天の罪人だ。人間世界から脱れることはできない。しかし、おまえといっしょに努力してこの世界から超越したいとは思っている"
"どうすれば超越することができるでしょうか"
"池を掘って魚を水に生かすように、道によって生きることだ。水を得て魚が水を忘れるように、道を得て道を忘れることだ"
"ところで"と子貢がさらに聞いた。"畸人(きじん)ということばがありますが、畸人とはどんな人間のことをいうのですか"
"畸人とは衆人と異なって、天と同格のものだ。ところが人の世では気違い扱いにされる。だから天の小人は人の君子、人の小人は天の君子というべきだろう。」(大宗師第六)
孔子のような徹底的なリアリストをさえ自分に都合のよいようにかってに創作してしまうぐらいだから、いかに荘子の意識のなかに孔子的要素が強く根を張っているか、うかがい知ることができるのではあるまいか。
さて、以上述べてきたように、荘子の生死一如観は実は彼の一元論から出発しているのである。有と無はつきつめていけば、混沌としたわけのわからないものであり、是と非はつきつめていけば、やはり混沌としたわけのわからないものである。このことを是認すれば生と死もまた同じように混沌としたもののなかに融け込んでしまう。
かかる究極のものは滅びることなく尽きることなく、知の思い及ぶところでもない。もし人間がそのなかに融け込んでしまうとすれば、かかる永遠の人間は、たとえ湖が焼けても焼けるわけがなく、たとえ銀河が凍っても、これが凍るわげがない。雷が山を打ちくだき、風が海を振動させても、これを驚かすことができない。かかる絶対者はあるいは雲に乗り、あるいは月日に騎し、どこへでも自由自在に行くことができると考えなければならぬ。
これは空想妄想というよりは、荘子的哲学の当然の帰結なのである。しかし、中国人の頭脳は非常に論理的にできているとはいえず、むしろ実感をもってでなければなにごとも受け付けないので、この理論にも人間的な肉づけをする必要があった。仏教と混淆して後世一般民衆の信仰の対象となった道教の神仙概念は、私の推測ではおそらく「荘子」に出発しており、また、唐代以後、文学上に現われる仙人や仙術は、いずれも荘子の思索から派生したものだと見ることができるのではなかろうか。一見、荒唐無稽に見えながら、その思索のあとを追究すると、今日の自然科学の思考方法ときわめて類似しているのを知りえて、興味がつきないのである。
|