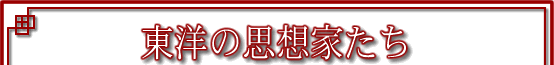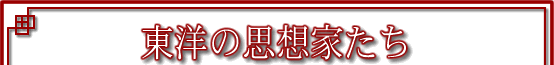|
しかしながら、目を世相に転ずると、これはまた収拾のつかない混乱の世の中である。
荘子の生きた時代は天下が分裂していわゆる弱肉強食の最も露骨に現われた時代で、個人の生命はそれこそ明日をも知れないものであった。にもかかわらず――いや、むしろそれだからこそ、人間はいよいよ実用を求め、いよいよ名利に走り、名誉や利益のために生命を賭けることを惜しまなかったのであろう。
よく老荘の哲学は、そうした世相のなかにあって、権力のないものが生きていくための、いわば弱者の哲学ないし処世術であるといわれている。「知足」をモットーとし、権力を嗤う老荘哲学の一面が結果として、失意の人や弱い者の慰めになったことは事実であるが、これまで述べてきたことからもわかるように、それは荘子の基本的なものの考え方の現実社会への適用にすぎず、権力者に対する反抗であるというよりは、儒教的な秩序観に対する反動の哲学として受け取るべきものであろう。
孔子の生きていた時代およびその死後しばらくのあいだは、孔子をよく言う人間よりも、むしろ悪しざまに言う人間のほうが多かった。しかし、その後、弟子たちの尽力により主として魯および齊でようやく儒学が盛んとなり、と同時に教祖としての孔子が偶像化されつつあった。
荘子がその著作のなかで孔子を「天から見はなされた罪人」と椰楡しながら、しかもしばしば孔子を自分の意見の代弁者として登場させているのは、いかなる企図に基づくものであろうか。おそらくそれは、荘子の真の敵は孔子その人ではなくて、孔子を教祖と仰ぐ教徒たちであり、孔子が必ずしも教徒たちの考えているような人物ではなかったことをことさらに示そうとしたのか、あるいは意識的に孔子の印象を撹乱させることによってその偶像化を防止しようとしたのか、のどちらかではあるまいかと私は想像している。人間世第四に出てくる孔子と顔回の次のような対話はその最も典型的な例であろう。
「顔回が孔子のところへ旅に出るからと挨拶に来た。
"どこへ行くのかね?"と孔子が聞いた。
"衛に行こうと思っています"
"なにをしに?"と孔子は重ねて聞いた。
"私の聞くところによると衛の王様はまだ年が若くてわがままなかただそうです。気ままな政治をやって過失を顧みず、また軽々しく人民を殺すので、死者が国じゅうにあふれているとのことです。先生はかねてから私に、よく治まっている国はどうでもよいから、乱れた国に行きなさい、病人の多いところには医者が必要だからと教えてくださいました。それで、これから先生のお教えを実行に移そうと思うのです"
"ああ、おまえには少し家賃が高すぎるよ"と孔子は言った。"おそらくは殺されるのがおちだろう。どうしてかというと、道は純粋でなければならないのにおまえは気が多すぎるからだ。気が多すぎれば、心配事が多くなって、自分さえ救うこともできないだろう。
自分の心さえ落ち着かせることができない者が、どうして暴君の行ないにまでそれを及ぼす余裕がありえようか。顔回よ。おまえは徳が名に失われ、知が争いから生まれるものであることを知っているか。名は互いにいがみ合うものだし、知は争いの武器だ。二つともいってみれば凶器だから、それが身を滅ぼす原因にならないとはかぎらないよ。それにたとえ徳があり信用されていても、また名声を争う気持がなくとも人の気心を察せず、仁義の押し売りをやれば、自分の美点をもって他人を傷つけることになる。こんな人はきっと災いを招くだろう。もしあの暴君が最初から賢者の言を耳に入れるような人なら、なにもわざわざおまえに聞くことはないはずだ。もしおまえが忠告すれば、彼はおまえの弱点につけ込んで逆におまえをやっつけようとするだろう。そのとき、おまえは心が動揺して、口はしどろもどろになり、思うことも言えなくなるだろう。これは火をもって火を救い、水をもって水を救うのと同じで、輸に輪をかけるようなものだ。はじめに一歩譲れば、際限なく譲らねばならなくなるし、信用されてもいないのに強いて忠言すれば必ずや殺されてしまうにちがいない。むかし、かの暴君桀王は関竜逢を殺し、紂王は比干を殺した。これは身臣下でありながら人民を愛し、逆に上の者を責めたからであって、暴君たちはこの二人がりっぱな人物であるがゆえにこれをおとしいれた。名を求める者はこういう結果を招く。またむかし、叢枝、胥敖は堯に滅ぼされ、有扈は禹に滅ぼされた。
これらの国王が国を失い身を滅ぼされたのは、兵を動かして実利を求めてやまなかったからだ。おまえもその話を聞いているだろう。名誉欲と物欲を克服することは聖人といわれている人々にとってさえむずかしいのだから、おまえにはとてもじゃなかろう。しかし、おまえがそれを知って行こうというからには、おまえなりの抱負があるかもしれない。それを話してごらん"
|