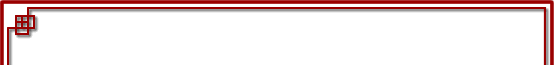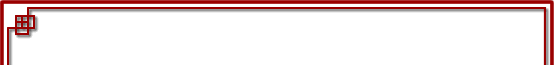|
では、実用を捨て名利を捨てることから、どれだけの得が生まれるだろうか。損得勘定をもって示さなければ、世間の人はそれを理解しないだろう。――と、たぶん荘子は考えたにちがいない。そこで彼は「無用の用」ということを具体的な例で示そうとした。
「匠石(石という名の大工)が齋の国を旅行して曲轅という所へ来た。そこには櫟の老木を祭った社があって、その大きさは牛の群れを覆いかぶせるほどもあり、また幹は百抱えほどの太さもある。しかも山を見おろすばかりの高さで、枝をちょっとながめただけでも舟が造れそうなのが十数本はありそうである。まわりには観光客がたくさん集まっていたが、匠石は振り返りもしないでとっとと歩きだした。弟子は飽きるまでじっとそれを見上げていたが、やがて匠石に追いつくと、
"私は斧をもって先生のあとについてまわるようになってから、こんなにみごとな木を見たことはありません。だのに、どうして先生は見ようともなさらないのですか"
"つまらんことを言うな"と匠石は答えた。"あれは役にたたない木だ。舟を造れば沈むだろうし、棺桶を作れば腐るだろう。また家具を作ればすぐに壊れ、門を作ればヤニを吹き出し、柱にすれば虫がつく、役にたたない木だからこそ、あれだけ長く無事でいられたのだ"
さて、家へ帰ってから、ある夜、櫟の老木が匠石の夢枕に立った。
"おい、匠石。おまえはいったい、おれをなにに比較しようとしているのだ。役にたつ木と比較しようというのか。考えてもみるがいい。柤、梨、橘、柚、果実、瓜のたぐいは、実がなるばかりに熟するともぎ取られたり、枝を折られたりひん曲げられたりする。みな、いずれも能あるがゆえに、自分の生を苦しめているではないか。天寿をまっとうすることができず、途中で夭折するのは自業自得というやつだ。その点おれはなんの役にもたつまいと思ってひたすらその努力をしてきた。死にそうになったこともあるが、いまはごらんのとおり大いに自分の役にたっている。もしおれが役にたっていたら、とてもこれだけ大きくはなれなかっただろう。おまえもみな同類なのに、おれの悪口を言うやつがあるか。いまにもくたばりかかっている役たたずに、どうしておれが役にたたない木だなどとわかるものか"
夢から覚めた匠石は、その話を弟子にして聞かせた。弟子が言った。
"自分から役だたないように努めた木がどうして社となって祭られるようになったのでしょうね"
"黙っておれ"と匠石はたしなめた。"社神のほうが木に身をよせただけのことで、なにも木のほうでそれを願ったわけではない。その証拠にたとえ社にならなくったって、切られはしないだろう。だいたい、あの木の考え方はほかの木とはわけが違うから、常識であれこれ言ったところではじまらないよ"」(人間世第四)
この木と同じ生き方は、人間でいえば、不具者や前科者やその他、世間から相手にもされないような人たちである。
「支離疏という男は世にも醜い片輸者で、あごはへそにかくれ、肩は頭より高く、髻は天を指している。五官は頭の上へあがり、腹と足が同じところにある。けれども針仕事と洗濯をすれば、なんとか糊口をしのぐにたり、箕で米をふるいわければ、けっこう、十人ぐらいは食わせていける。ところがお上で徴兵があると、支離疏は兵隊たちのあいだを歩きまわってうれしそうに腕を振り、お上が工事の人夫を徴用するときには体に病気があるので免除される。反対にお上で病人に粟を恵むときは三鍾の米と十把の薪がもらえるのである。形が醜くできた支離ごとき人間でさえその身を養って天寿をまっとうすることができるのだから、まして精神的支離は言うを要しないであろう」(人間世第四)
では、荘子が実際に支離疏のような男のほうが幸福であると考えていたかというと、これは大いに疑問であろう。片輪であることの不幸はおそらく正常人の想像も及ばないものであろうし、いかなる悟りもこの不幸をカバーして禍を福に転ずるだけの力がないかもしれないのである。けれども、険しい世相のなかで人を踏みつぶして生きようともがく人間に比べれば、こうした片輪者のほうがまだましだと荘子は皮肉ったのであろう。そして、荘子的な論法をそのままここで使うことを許されるならば、かような文学的表現はあふれるような才能があってはじめて可能なものであるから、この処世訓を拳々服膺すべき人は、実は誰よりも荘子自身だったにちがいないのである。
|