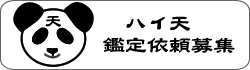| 第170回
私のお気に入りの一品
今回の私のお気に入りの一品は
「定窯 白磁刻花碗」です。
定窯とは河北省に存在し、
主に宋時代に名声を轟かせた白磁の名窯です。
この定窯は、1941年に日本人陶磁学者である
小山富士夫氏によって発見されます。
小山富士夫氏は日本を代表する中国陶磁器研究者ですが、
定窯の発見はじめ多くの功績を残されておられます。
実は、小山氏が定窯を発見したのは、
日中戦争の真っ只中でした。
そういう状況の中、戦争に目を向けず
ひたすら「今こそチャンスだ」と
中国の名窯の窯跡を調査した熱意には驚かされます。
そこまでして、多くの学者が追い求めた定窯とは
どんな窯だったのでしょうか?
簡単に言えば、定窯とは
「世界で最初に硬質の白磁の大量生産に成功した窯」
だと言えます。
今、私たちの周りに存在する白くて硬い焼き物・・
その原点は中国河北省に生まれた定窯にあるのです。
勿論、唐時代にはすでに
とても綺麗な白磁の焼成に成功していましたが、
日常の使用に耐え得る硬質磁器の量産に成功したのは
定窯が始めてでした。
これに成功した理由には、いくつかの発明があります。
第一に、「伏せ焼き」という技法です。
この焼成法の確立により、
一度に焼ける陶磁器の数は飛躍的に伸びました。
更に「伏せ焼き」を成功させる為に必要な
「こしの強い胎土」と「火力の強い薪」が
当時の華北地方一体でたくさん採れた事も
定窯が成功した大きな理由です。
また、定窯の白磁の第一の特徴としては「牙白色」という、
象牙のような少し黄ばんだ白色の発色があります。
現在、この何とも言えない「牙白色」が素晴らしいと評価され
定窯は評価されていますが、
実はこれはたまたま焼成に使われた「薪」の不足によって、
仕方なく代用とされた「石炭」の酸化焼成での副産物なのです。
北宋初期に焼かれた定窯の作品は
透明感のある白色にカリっと焼き上がっていますが、
時代が下がる作品にはこの牙白色の発色が多くなり、
更に「涙痕」と呼ばれる釉薬のたれ跡が見られるようになります。
現代人にとって、その「涙痕」が更に定窯の魅力となり、
定窯の白磁は高額で取引きされています。
「牙白色」も「涙痕」も
実はある意味失敗から生まれた器物の特徴なのにです。
今回紹介する作品は「牙白色」と「涙痕」、
両方の特徴を持った典型的な作品と呼べるでしょう。
 |
典型的な定窯の作品
刻花と呼ばれる削り出し文様で装飾している。 |
 |
定窯独特の「涙跡」
このような感じの作品に偽物はない。 |
--- 天青庵さんよりお知らせ ---
あなたの自慢のお宝をスバリ鑑定いたします。
中国古陶磁器はじめ中国に関するものなら何でもけっこうです。
お気軽にどしどしご応募下さい。
(詳細はこちらの申し込み欄を読んで下さい) |