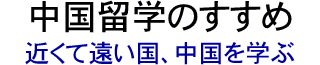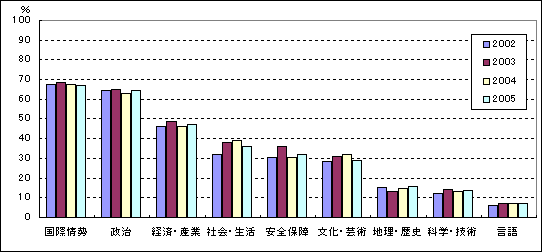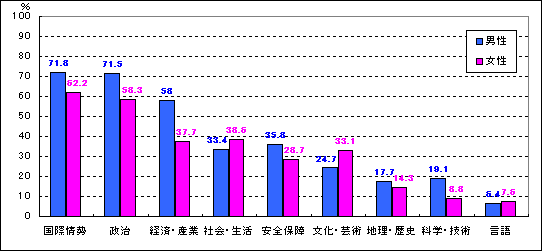|
第112回
日本人が入手している外国情報の内容
昨日からの続きです。
さて、人々が入手している外国情報の内容は、
一体どういった種類のモノの比率が高いのでしょうか?
|
- 外国情報の入手内容と比率の推移 -
|
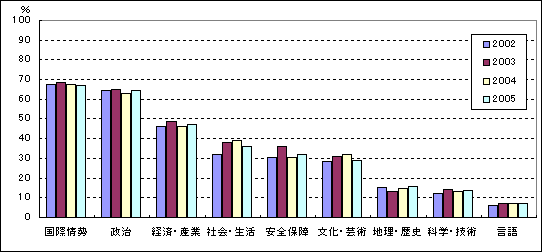 |
2002年から2005年までの
外国情報の入手比率の推移をみてみると、
同一の外国情報に対する入手比率の変動は
小さいことが分かります。
人々が関心のある外国情報は、
どうやら一朝一夕には変わらないようです。
しかし、同じ内容の外国情報でも、
男女によって、その入手比率に違いがあるようです。
|
- 外国情報の入手比率(男女別) -
|
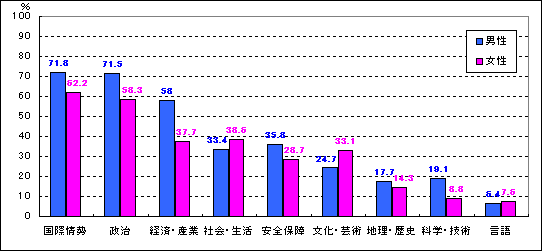 |
こうして統計データを見ていく楽しみの一つに、
各セグメントの特性の違いが現れた時に
「意味のありそうな差異に、ワクワクする」
というものがあります。
(私だけでしょうか?)
「国際情勢」「政治」「経済・産業」「安全保障」
「地理・歴史」「科学・技術」といった
やや硬い雰囲気のトピックスに対しては、
男性の関心がやや高いようです。
逆に、「社会・生活」「文化・芸術」「言語」といった
どちらかというとソフトな話題には、
女性の関心が高い傾向が見受けられます。
また、男女ともに各メディアから摂取する情報には、
「各国への親近感」や「日本と諸外国との関係性」
に関する意識に対し、
直接的に影響を与える情報の入手比率が高いことが分かります。
これまでみてきたように、
人々の外国情報の仕入先は「マスコミ4媒体」のうちの
「テレビと新聞」がその大勢を占めます。
これらのメディアにおいて、
バランスを欠いた情報が溢れてしまうと、
人々の諸外国への思考形成にも
多大な影響がもたらされることでしょう。
情報の受け手である生活者は、
それぞれのメディアが持つ性質を今一度考え直し、
情報を摂取する際に、
客観的な受け止め方をする必要がありますね。
また、ただ情報を一方的に受け取るだけでなく、
日常生活の中で情報を取捨選択し、発信していくことも、
他の人々の「考える材料の幅」を広げことに
寄与することでしょう。
|