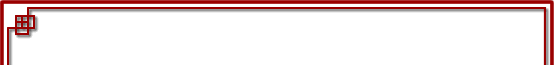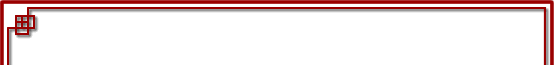人間は感情の動物であることを孔子は否定しない。そして、人間の感情には強さや弱さがあり、また相手しだいで現われ方が違ってくる。だから彼は人を愛せよと言っても、すべての人を平等に、なんじ自身の敵をも愛せよ、などとは言わない。ある人が、
「怨に報いるに徳をもってするということばがあるが、どうですか」と聞いたら、
「じゃ、徳にはなにをもって報いるのかね?」
と彼は反問した。怨みに報いるに徳をもってしたら、徳をもって自分を遇した人に対して不公平だと彼は考えているのである。
「徳には徳を、怨には正しさをもって報いることですね」と彼は答えた。
正しさ(直)ということばははなはだ含みのある、曖昧なことばであることはいうまでもない。つまり孔子は普遍的な、常套的な愛は人間の本能に根ざさない「空虚な」感情であることを知っており、それゆえに、それをもっていっさいを律することを避けたのである。「目には目を、歯には歯を」とまでは言わないけれども、自分の感情を納得させることのできるような自由な判断に任せよ、と逃げているのである。
ここにも私はリアリストとしての孔子を見る。もし孔子が、今日なおわれわれにとって依然魅力的な存在だとすれば、それは彼のこうした「実際感」がわれわれを打つからではあるまいか。
とすれば、われわれは、孔子ののこした数多い金科玉条の裏に、感情家としての孔子の姿を見いだすことができるはずである。
たとえば、孔子は「知識のある者は惑わず、徳のある者は憂えず、勇気のある者は恐れず」と言っている。それは結論としておのずから生まれたことばであるが、そこに至るまでの過程において、孔子は惑い、憂え、そして恐れたにちがいない。自分は「怒ると飯がのどをとおらない」「泣くと、その日は歌を歌わない」と白状しており、弟子の顔回が「怒ってもあたり散らさず」「間違いを起こしても二度と繰り返さない」のを美徳として賞めているのは彼自身がよくあたり散らし、よく間違いを繰り返したからと解釈すべき性質のものであろう。なぜならば、自分に備わっているものは概して美徳と思えないのがふつうであり、後天的にそれを身につけようと努力したところに、孔子の真価があるからである。
「人間は生まれたときはどれも似たようなものだが、習慣や環境でしだいに遠ざかっていく」「とはいえ、バカは死ななきゃなおらない」「自分は生まれながらになにもかも知っているわけではない。歴史が好きで、神経質になって、これを求めたからだ」
感情家孔子が迷うのは生理的必然というべきである。 |