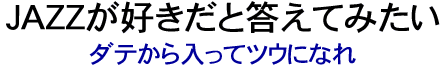|
第61回
哀愁漂うマイナー・ブルース
引き続き、ジャズの名ブルースを紹介します。
今回はマイナー・ブルースを紹介しましょう。
ブルースの調性は、通常はメジャーです。クラシックで言えば長調。
つまり、明るいか暗いかと二者択一で問われれば、
“明るい”に属する調性ですね。
明るいのに、なぜ、ブルースには
一口に明るいとは言えない複雑な陰影があるのかというと、
メロディはマイナーの音使いをすることが多いからです。
つまり、左手では“ド・ミ・ソ”と
明るい調性の和音を抑えているのに、
右手のメロディは“ミ”の音ではなく“ミ♭”の音を奏でる。
鍵盤を押してもらえば分かると思いますが、
ミとミ♭の音を同時に押すと不協和音的な響きになります。
しかし、この明るさと暗さのぶつかり合いこそが、
ブルースの特徴でもあるんですね。
この“ミ”から半音フラットした“ミ♭”の音は、
黒人独特のメロディ感覚で、ブルーノートと呼ばれています。
レーベルのブルーノートではありません。
ブルー、つまり憂鬱な、
あるいはメランコリックな音(=ノート)といった意味です。
調性内で使われている音よりも、
ピッチ(音程)の下がった音を使用すること。
これは、クラシックの理論からすると、明らかに“間違い”ですが、
ブルースにおいては、
陰影に富んだニュアンスを醸し出すスパイスのようなものなのです。
だから、通常ブルースは、調性はメジャー、
メロディはブルーノートを交えた暗い音を使うことが多いのですが、
例外もあります。
マイナー・ブルースです。
これは、左手の調性も最初からマイナー(短調)。
だから、曲のニュアンスも
通常のブルースよりもよりダークなムードになります。
曲によっては、より演歌チックになるかもしれません。
さて、前置きが長くなりました。
代表的なマイナー・ブルースを紹介します。
ジョン・コルトレーン(ts)の《ミスター・P.C.》。
名盤『ジャイアント・ステップス』に収録されています。
P.C.とは、この演奏に参加しているベーシスト、
ポール・チェンバースのイニシャルです。
つづいて、56回でも紹介したルー・ドナルドソン(as)の
《ブルース・ウォーク》。
マイナーならではの、哀愁感漂う名ブルースです。
あまり有名ではないかもしれませんが、
私が個人的に愛聴しているのが
ケニー・ドリューの《グルーヴィン・ザ・ブルース》。
これは、『アンダー・カレント』という
アルバムに収録されていますが、
まったりと重い濃厚な空気を味わえる名ブルースです。
最後に、これは非常に日本では有名なブルースですが、
ベニー・ゴルソン作曲の
《ファイヴ・スポット・アフター・ダーク》。
名前は知らなくとも、みなさんも一度は耳にしていることでしょう。
これは、カーティス・フラー(tb)の
『ブルース・エット』というアルバムに入っています。
以上、駆け足で代表的なマイナー・ブルースを紹介しました。
引き続き次回も、もう少し、ブルースについてお話させてください。
――――――――――――――――――――――――――――
『ジャイアント・ステップス』
ジョン・コルトレーン |
1.ジャイアント・ステップス
2.カズン・マリー
3.カウントダウン
4.スパイラル
5.シーダズ・ソング・フルート
6.ネイマ
7.ミスターP.C.
8.ジャイアント・ステップス
9.ネイマ
10.ライク・ソニー
11.カウントダウン
12.カズン・マリー
13.シーダズ・ソング・フルート
|
練習の鬼、ジョン・コルトレーンの修行と鍛錬の結果が結実した、
凄まじいまでの気迫と音符の数が凝縮されている名盤。
ポール・チェンバースに捧げられた《ミスター・P.C.》だが、ベースソロはない。
彼のウォーキング・ベース(1小節に4つを刻むバッキング)のほうに
敬意を表していたのかもしれない。
肉厚で重厚な《グルーヴィン・ザ・ブルース》。
晩年、日本人にスタンダードばかりを弾かされていたドリューとは一味も二味も違う、
硬派で重量級のドリューを味わえる名盤で、
個人的には、ブルーノートのベスト10に入れたいアルバムです。

『ブルースエット』
カーティス・フラー |
1.ファイブ・スポット・アフター・ダーク
2.アンディサイデッド
3.ブルースエット
4.マイナー・バンプ
5.ラヴ・ユア・スペル・イズ・エヴリホエア
6.12インチ |
トロンボーンのほんわりとした暖かいメロディとベストマッチなこのメロディ。
哀愁たっぷり、しかし、どこか暖かい演奏が多くのリスナーの心を捉えました。
|